2026年に変わる日本農業:政策転換とトレンドが描く新しい風景

1. 政策転換期における日本農業の位置づけ



1-1. 「食料安全保障」としての農業再定義
2025年以降、日本の農業は単なる「産業」ではなく、食料安全保障を担う戦略的インフラとして再定義されつつあります。
ロシア・ウクライナ情勢や輸入飼料・肥料価格の高騰、新興国の食料需要拡大により、「国産で賄う力」が求められる時代へと変化しました。
政府はこの流れを受け、2026年度にかけて「農地の集約化・国産穀物強化・次世代農業人材育成」を重点政策に据えています。
特に食料自給率の向上(2024年度はカロリーベースで37%)を目指し、米や小麦、大豆などの国内生産拡大策が強化されています。
1-2. 予算・制度改正の方向性
農林水産省の2026年度概算要求では、スマート農業の導入支援、再生型農業(リジェネラティブ農業)の拡充、農業のDX化が柱となっています。
また、「農業経営基盤強化促進法」の改正により、農地の大区画化・集約化を進めやすくする仕組みも整備される見込みです。
特に注目されているのが、中山間地域での「地域営農組織」支援制度。
小規模農家の経営継続を支える新たな政策パッケージとして、地方自治体と連携した補助金・助成金が2026年に本格化します。
1-3. 政治体制の変化と農政への影響
農政の方向性を左右するのは、政治の舵取りです。2025年には新しい農林水産大臣が就任し、**「地方創生と農業の一体改革」**を掲げています。
与党・自民党内でも「農地政策推進議連」や「食料安全保障調査会」などが活発化しており、農業は政局の重要テーマになっています。
2026年は「選挙と農政」が重なる年。地方選挙や国政選挙の動向次第で、農業予算や補助制度の方向性が変化する可能性もあります。
政治と農業の距離がこれほど近くなったのは、食料問題が“国防”に近いテーマになっているからです。
2. 技術・品目・経営の「三位一体」トレンド



2-1. スマート農業と政策支援の融合
2026年の農業トレンドを語るうえで欠かせないのが、スマート農業の全国展開です。
AI・IoT・ドローン・自動運転トラクターといった技術が、補助金制度の後押しを受けて一気に普及し始めています。
農林水産省は「スマート農業実証プロジェクト」を全国100地域以上に展開。
2026年度は、省力化と高収益化を両立できるモデル経営体を重点的に支援する方針です。
また、スマート農機メーカー各社(クボタ・ヤンマー・井関など)も、政策連動型の新商品を続々投入予定です。
2-2. 米政策の転換と多様な作目へのシフト
長年、米政策は「減反」と「生産調整」を軸にしてきましたが、2026年以降は需給連動型の柔軟政策に転換します。
具体的には、米の過剰在庫を抑えつつ、飼料米・輸出米・業務用米の生産を拡大。
「食料自給率の柱」としての米づくりが、再び注目を集めています。
同時に、政府は「地域特化型作目振興制度」を通じて、野菜・果樹・畜産・施設栽培などの多様化も支援。
特に温室ハウスによるトマトやイチゴの周年栽培、垂直農法の実証など、都市部でも農業が再構築されつつあります。
1-3. 政治体制の変化と農政への影響
農政の方向性を左右するのは、政治の舵取りです。2025年には新しい農林水産大臣が就任し、**「地方創生と農業の一体改革」**を掲げています。
与党・自民党内でも「農地政策推進議連」や「食料安全保障調査会」などが活発化しており、農業は政局の重要テーマになっています。
2026年は「選挙と農政」が重なる年。地方選挙や国政選挙の動向次第で、農業予算や補助制度の方向性が変化する可能性もあります。
政治と農業の距離がこれほど近くなったのは、食料問題が“国防”に近いテーマになっているからです。
3. 政策のジレンマと課題
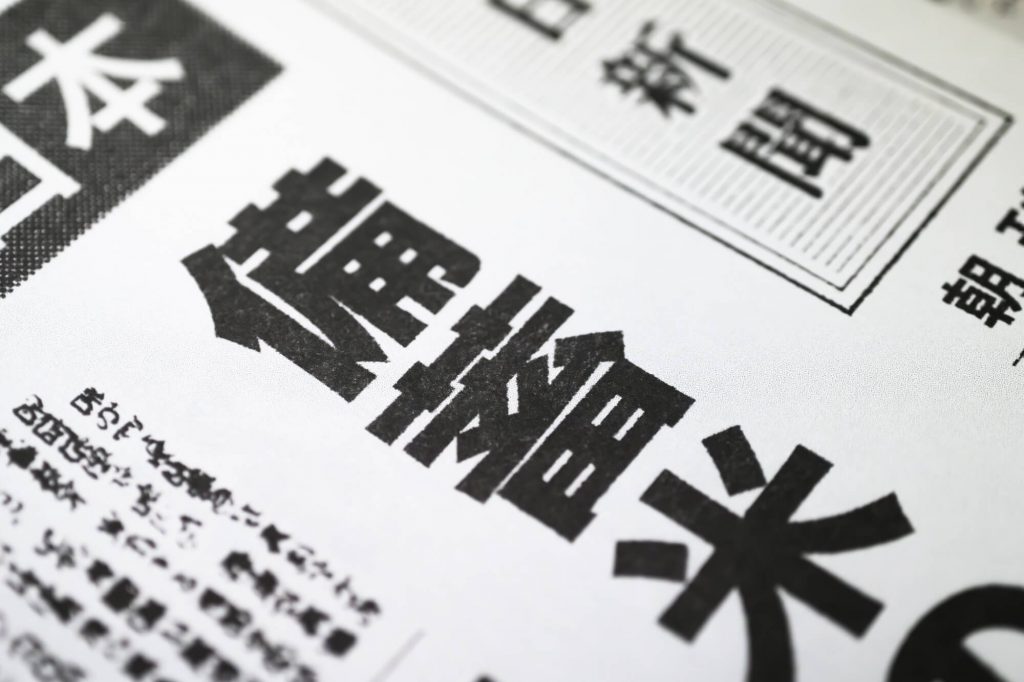
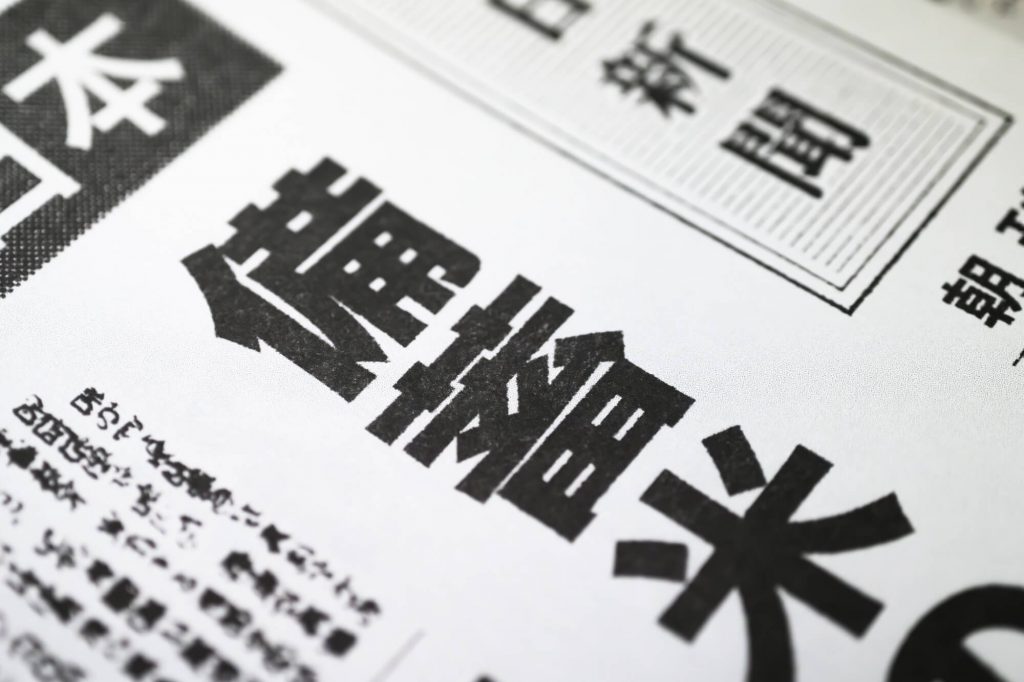
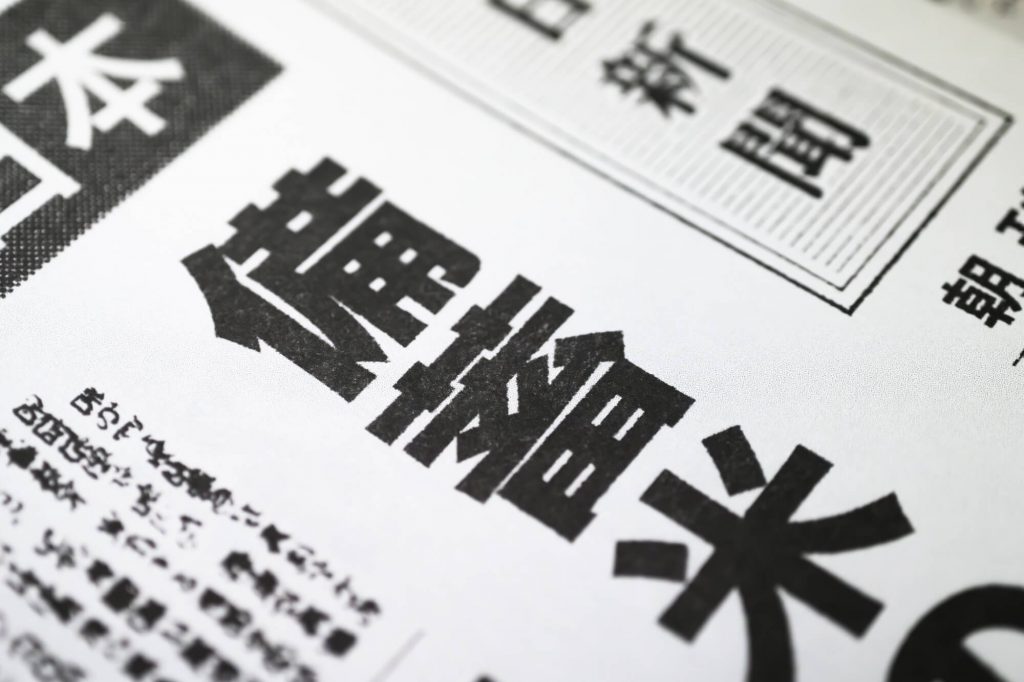
3-1. 米政策の“ジレンマ”
米の供給過多を防ぐための生産調整が緩むと、価格下落リスクが高まります。
逆に、減反を強化すれば自給率が下がる。この二律背反が、農政の根本的な課題です。
2026年には、AIを活用した需給予測モデルが導入される見通しですが、
実際の市場調整には地域差や作況が大きく、現場の混乱を防ぐには慎重な制度設計が求められます。
3-2. 中山間地・小規模農家の取り残され問題
スマート農業・大区画化は効率的ですが、資金・人材・技術の面で小規模農家がついていけない現実があります。
この「格差拡大」を是正するため、政府は地域営農組織への支援と、農業高校・専門学校との連携を強化しています。
しかし、地方の高齢化は深刻で、2026年時点で農業従事者の平均年齢は約68歳。
“担い手”の確保と“事業継承”が、農政の最大の課題といえます。
3-3. 食料価格と国民生活への影響
食料自給率を上げるには国産品の価格上昇を受け入れる必要があります。
これは消費者にとってのコスト上昇につながり、政治的な判断が問われます。
政府は「食料安定供給特別交付金」や「価格安定支援制度」を整備し、急激な価格変動を抑制する方針です。
しかし、輸入依存を脱するには、消費者・生産者・政治の“合意形成”が欠かせません。
4. 2026年に向けて取るべき戦略
4-1. 政策補助を「戦略的」に活用する
農家が最初に行うべきは、自分の地域で利用できる補助制度を知ることです。
スマート農業実証事業、地域農業経営支援交付金、再生型農業促進補助など、
国・県・自治体が用意する補助メニューは多岐にわたります。
4-2. トレンドを見据えた品目・経営モデルへの転換
2026年以降、農政は「環境×デジタル×収益性」の三本柱で動きます。
たとえば、炭素吸収量を数値化しカーボンクレジットを販売する“炭素農業”や、
地域ブランドと観光を組み合わせた“6次産業化”などが有力です。
4-3. リスクに強い経営へ
気候・市場・政策が不確実な時代には、「単一依存型」経営はリスクが高いです。
複数の作目、直販・加工・オンライン販売を組み合わせる多角経営モデルが求められます。
政策が追い風となるうちに、次の一手を打つことが2026年の鍵です。
結論:政策転換が提示する“次の農業像”
2026年の日本農業は、**「政治主導の構造改革期」**に入ります。
補助金や制度が増える反面、選択と集中が求められる時代でもあります。
農業を「守る産業」から「創る産業」へ――。
その転換を支えるのが、政治と農政の力です。
農家・事業者が政策を“読む”力を持てば、未来の農業経営は確実に変わります。
2026年の農業政策で、農家に最も影響が大きいのはどの部分ですか?





最も大きいのは「農地集約化・大規模化」を促す政策です。 農地バンク制度の機能強化や、貸し借りの仕組みがより柔軟になることで、企業や大規模法人が農地をまとめやすい環境が整います。一方で小規模農家は、地域営農組織に参加することで政策の恩恵を受けやすくなります。
企業や異業種の農業参入は2026年さらに増えますか?





はい。企業参入は大幅に増える見込みです。農地利用制度の緩和に加え、データ農業・環境ビジネス・カーボンクレジットなど、異業種が入りやすい新市場が広がっています。特にIT、エネルギー、建設業などからの参入が増えると見られます。
農業政策の変化によって、価格の安定性はどう影響しますか?





「価格の安定策」は強化され続ける方向です。米・小麦・大豆などは政府の需給調整が入り、野菜は全国的な生産調整システムの導入が予定されています。ただし、国際市場の価格変動が依然として大きいため、完全な安定は難しく、リスク管理の重要性は増す見込みです。

















