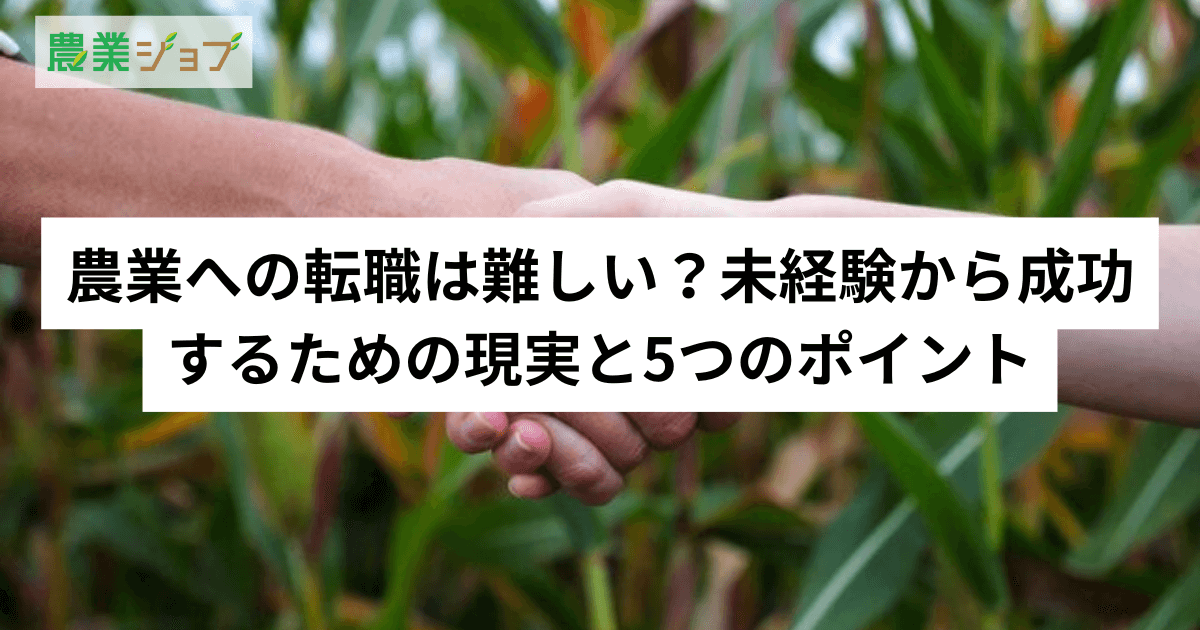オリーブ農家の年収は?新規就農に向けた収益モデルと成功のポイント
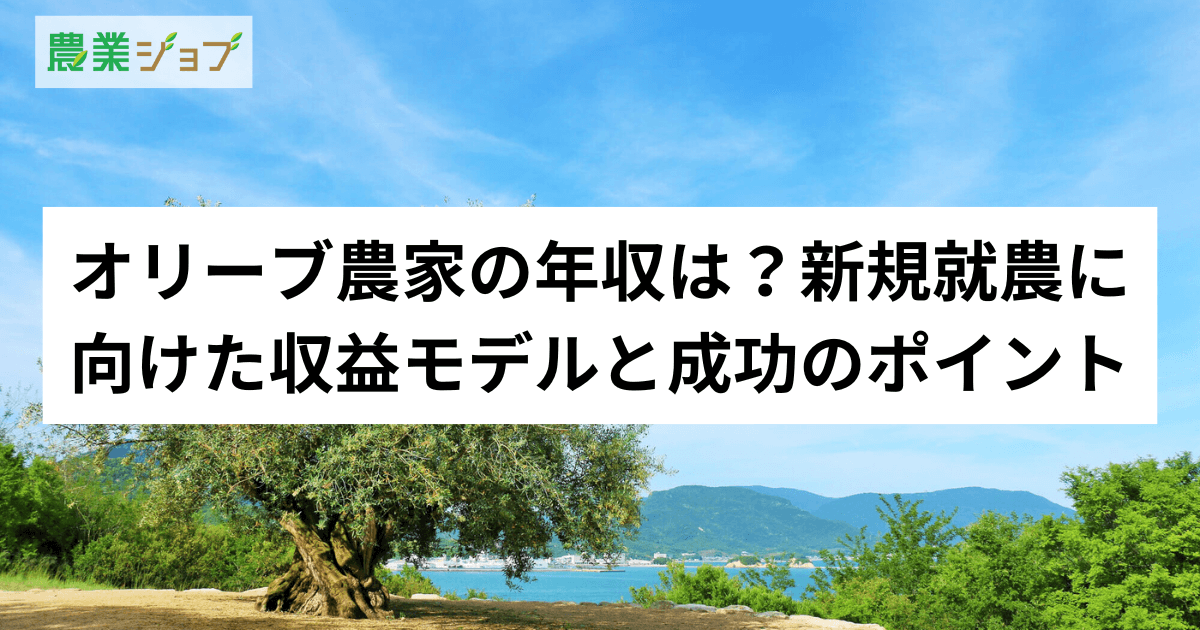
オリーブ農家とは?基本情報と国内の現状
オリーブの木を栽培し、その実から得られる果実やオイルを販売して収入を得るオリーブ農家が日本でも広がりを見せています。オリーブは地中海性気候を好む作物ですが、近年では日本国内でも温暖な地域ではしばしばオリーブ栽培が見られます!
特に香川県・小豆島は、日本におけるオリーブ栽培のパイオニアとして有名で、現在も国内最大の生産地です。さらに、和歌山県や鹿児島県、岡山県などの地域でもオリーブ栽培が盛んになっており、気候変動や作物の多様化を背景に、新たな地域での挑戦も増えています。



また、オリーブは苗を植えてから実がなるまでに数年の時間を要します。新しく始めるには確かにハードルが高いバイトですが、収穫が始まれば長期にわたって安定的に生産ができるというメリットがあります。この「中長期的な収益化の可能性」や「付加価値の高い商品展開がしやすい」という特徴から、新規就農者にとっても魅力的な作物として注目されています。
一方で、栽培には独自の技術や管理が必要であり、適切な剪定や病害虫対策など、継続的な学びも欠かせません。国内での情報やノウハウはまだ限られている面もありますが、それゆえに新規参入者が差別化しやすいという側面もあります。
オリーブ農家の平均年収と収益の内訳



オリーブ農家の年収は、農園の規模や経営スタイル、販売形態の有無によって大きく変わります。特に新規就農者にとっては、「どれくらいの収益が見込めるのか?」という点は非常に気になるところでしょう。
まず、小規模(約0.5〜1ha)のオリーブ農園では、オリーブオイルや加工品の販売を含めた年間収益は数十万円〜200万円前後が目安です。収量や品質、販路によってばらつきがありますが、自家販売やECサイトを活用することで収益を上げている事例もあります。
一方、中規模(1〜3ha)になると、収穫量が安定し、加工作業や販売戦略が軌道に乗れば年収500万〜800万円を狙えるケースもあります。自社ブランドのオイルを作ったり、観光体験型農園として展開することで、付加価値を高める工夫がされています。
さらに、大規模(3ha以上)で法人経営や6次産業化に取り組んでいる農園では、年収1,000万円以上を達成している成功事例も存在します。ここまでくると、単なる農業経営にとどまらず、「農業×商品開発×マーケティング」という総合力が求められます。
収益の内訳としては、以下のような構成が一般的です:
1.オリーブ果実の販売(地元市場、業者卸など)
2.オリーブオイルの製造・販売(自社製造または委託製造)
3.加工品の販売(オリーブの塩漬け、化粧品原料など)
4.観光農園や農業体験の提供(入園料、物販など)
5.オンライン販売・ふるさと納税返礼品(オンラインサイトや自治体との連携)
このように、オリーブ農家としての年収は「作る」だけでなく、「どう売るか」によって大きく左右されます。収益の柱をいくつ持てるかが、安定経営のカギとなります。
オリーブ農園経営に適した土地とは?



苗木、農機具、土地の取得・整備コスト
年間の維持費や作業の労力
オリーブは地中海性気候を好む作物で、日照時間が長く、降雨量が少なく、冬の寒さが厳しくない地域に適しています。そのため、日本国内では温暖で乾燥しやすい瀬戸内海沿岸や南西日本の一部地域がオリーブ栽培に適しているとされています。
代表的なオリーブ栽培地域
香川県(特に小豆島)
日本で最も有名なオリーブの産地であり、100年以上の栽培の歴史を持っています。県としてもオリーブ産業を推進しており、新規就農者への支援制度も充実しています。
和歌山県
みかんの栽培で有名な地域ですが、温暖な気候を活かしてオリーブの栽培にも力を入れています。特に南部の地域で栽培が盛んです。
鹿児島県
南国の気候を活かし、オリーブ栽培の新たな産地として注目されています。特に肝付町や指宿市などで栽培面積が増加中です。
岡山県
瀬戸内の温暖な気候に加えて、水はけのよい土壌がオリーブに適しており、近年では生産量も増加しています。
三重県、愛媛県、広島県など
いずれも瀬戸内海や太平洋に面しており、気候条件がオリーブに合っているため、農業振興の一環として取り組みが進んでいます。
地域選びのポイント
オリーブ栽培を考えるうえで重要なのは、「気候」「土壌」「販路」の3つです。オリーブは水はけのよい土壌を好み、過湿に弱いため、水害リスクの少ない地域が適しています。また、農産物のブランド力や観光資源と組み合わせやすい地域では、収益の多角化も図りやすくなります。
将来的な販路や加工施設の有無、地域の支援体制なども考慮しながら、就農地を選ぶことが成功への第一歩となります。
国産オリーブの強みとは?



世界的に見れば、オリーブはスペインやイタリア、ギリシャなどの地中海諸国が有名な産地ですが、近年では「国産オリーブ」の注目度が高まっています。日本国内で生産されたオリーブには、輸入品にはない強みや価値が多くあります。
1. 鮮度の高さと香りの豊かさ
国産オリーブオイルの最大の特徴は、圧倒的な鮮度。収穫後すぐに搾油されるため、果実本来の香りと味わいがダイレクトに残ります。これにより、フレッシュで青々とした風味が特徴の「初摘みオイル」は、国内外の料理人や健康志向の消費者に高く評価されています。
2. 生産者の顔が見える安心感
国産オリーブは小規模経営が多いため、生産者のこだわりや栽培ストーリーが明確に伝えられるのも魅力の一つです。化学肥料や農薬の使用を控えた安心・安全なオリーブ栽培を行う農家が多く、トレーサビリティ(生産履歴の追跡性)も高い点が信頼を集めています。
3. 高品質路線での差別化が可能
国産オリーブオイルは、量では輸入品に及ばないものの、品質で勝負する「プレミアム商品」としての地位を築きつつあります。国際的な品評会での受賞歴も増え、高価格でも“選ばれるオイルとしてのブランド価値が高まっています。
4. 日本人の味覚に合うバランス
海外のオリーブオイルに比べて、国産オイルはクセが少なく、まろやかな味わいが特徴とされています。和食にも合わせやすく、家庭料理でも取り入れやすいため、需要の拡大が期待できます。
5. 地域ブランドとの連携による付加価値
香川県小豆島のように、「オリーブ=地域の名産品」としてブランディングされている例もあり、ふるさと納税や観光商品との連携で地域経済に貢献できる農産物としても注目されています。
まとめ
オリーブ農家は、他の農作物とは異なる魅力と将来性を秘めた分野です。収益性の面でも、栽培規模や販路の工夫次第で安定した収入を目指すことができ、6次産業化や観光との連携によって多様なビジネス展開も可能です。
また、国産オリーブならではの強みや地域ブランドとの相性の良さも、新規就農者にとって大きなチャンスと言えます。もちろん、成功には知識と準備、地域の情報収集が不可欠ですが、「自分らしい農業」を目指す人にとって、オリーブは理想的なスタート地点と言えるでしょう!!
農業ジョブでは全国のオリーブ農家を含めた新規就農者を募集しています!
全国のオリーブ農家の求人募集はこちら!!
オリーブ農家の平均年収はどのくらいですか?





規模や経営スタイルによって大きく異なりますが、一般的には以下のような目安です。小規模農園(0.5〜1ha)、年間数十万円〜200万円前後、中規模農園(1〜3ha)、年間500万〜800万円程度、大規模農園(3ha以上・法人経営含む)、年間1,000万円以上の例もあり、自家販売やブランド化による販路の工夫で収益は大きく変動します。
国産オリーブの強みは何ですか?





国産オリーブには以下のような強みがあります。圧倒的な鮮度と香りの良さ(収穫直後に搾油できる)生産者の顔が見える安心・安全な栽培というメリットがあります。また、高品質でプレミアム市場向けの販売が可能で日本人の味覚に合ったまろやかな風味が魅力です。地域ブランドや観光との相乗効果も期待できます。
どの地域がオリーブ栽培に向いていますか?





温暖で乾燥気味の気候が適しており、以下の都道府県が代表的です。香川県(特に小豆島)、和歌山県、鹿児島県、岡山県、愛媛県、広島県などが挙げられます。瀬戸内海沿岸などこれらの地域では自治体の支援体制も整っている場合が多く、新規就農者には心強い環境が揃っています。。