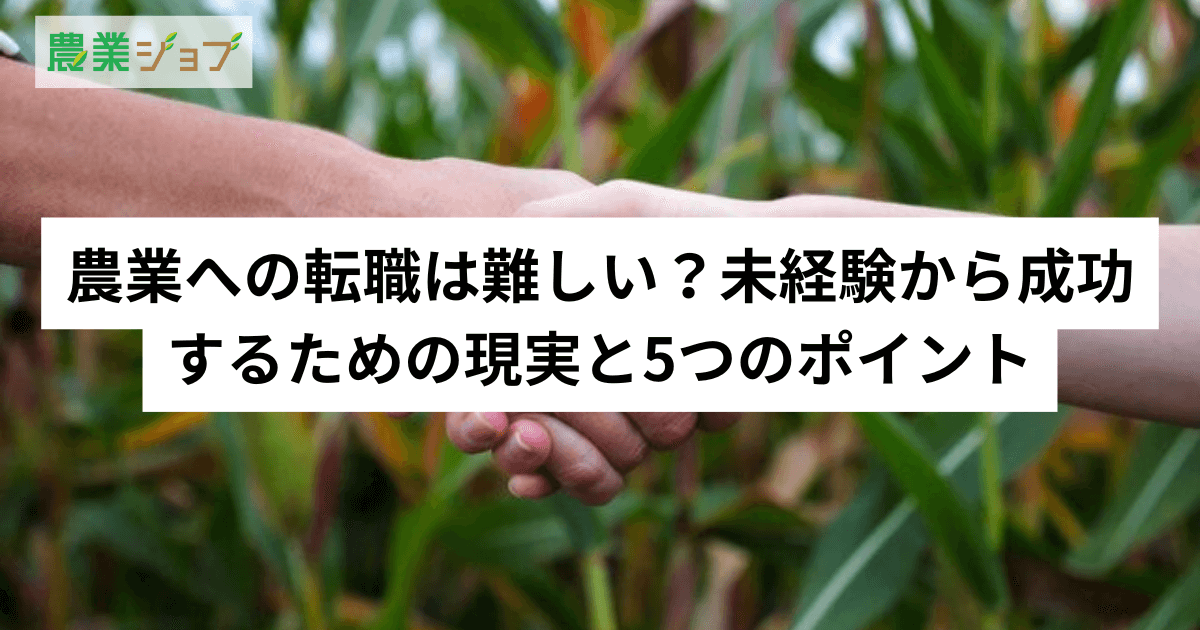農福連携とは?農業を活用した福祉の新しいカタチについてわかりやすく解説!

農業分野と福祉分野が手を結び、農業の担い手づくりと障がい者の社会参画をめざす「農福連携」。最近は障がい者だけではなく、生活困窮者や高齢者なども含む、だれもが生きやすい社会を実現する取り組みとしても注目されるようになりました。今回は、農福連携によるメリットと取り組みが広がった背景や今後の展開をご紹介します。
農福連携とは?
あらゆる人が働くことのできる環境を
農福連携とは、だれもが生きやすい「共生社会」を実現するために、農業分野と福祉分野が連携した取り組みです。具体的には、障がい者や生活困窮者など、社会で生きづらさを感じている人たちに農業を通じて、就労の機会や生きがいとなる場を作ることが狙いです。
農業労働力の不足や荒廃農地の存在といった農業分野での課題と障害者等の就労先の確保の必要性といった福祉分野での課題を接続して解決を図る取り組みになっています。
農福連携の始まり
障がい者が農場で働く例は以前からありましたが、2016年に「共生社会」をつくるという観点から農福連携の推進計画が政府の施策に盛り込まれると、「農福連携」という言葉が少しずつ広まり、現在では官民挙げて取り組む事業として位置づけられるようになりました。
2024年には農林水産省が農福連携等推進ビジョン(2024年改訂版)が決定され、地域ごとの課題への対応や認知度の更なる向上に焦点が当てられ取り組みが拡大しています。
障がい者の就職先としての農業
では、障がい者が働く場の一つとしてなぜ「農業」が注目されるようになったのか、その理由をみてみましょう。
農業には、農場管理、収穫、出荷などさまざまな仕事がありますが、こうした作業は「草取り」「出荷調整」「袋詰め」など、障がい者の適正に合わせてさらに細分化することが可能です。また、体を動かすことでリハビリとしての効果も期待できるほか、継続して働くことで工賃が上がれば、働く喜びや生きがいにもつながります。
仕事を求める障がい者は年々増えており、厚生労働省が発表した2019年度のハローワークを通じた「障がい者の職業紹介状況等」によると、就職件数は11年連続で増加、新規求職申込件数は前年度比5.7%増となっています。
こうした状況を背景に、障がい者が働きやすい就職先として農業にも注目が集まるようになりました。現在では、全国で4,117実施主体(農業法人、社会福祉法人、民間企業等、特別支援学校等)が農福連携に取り組んでいます。(2021年3月現在 ノウフクWEBより)
農福連携の拡大
元々、農福連携とは農業分野において障がい者の就労機会を充実させる取り組みでしたが、今では障がい者以外にも生活困窮者や高齢者、犯罪歴のある人や引きこもりの人など通常の就労が難しい人に向けにも農福連携の窓口が広がっています。
農福連携は地域社会とも連携し、農業と福祉の力によって若手の労働力が不足している高齢化している地域においての雇用機会の創出など持続可能な地域社会の実現に尽力しています。
農福連携のメリットとは?
どちらにもメリットがあるWin-Winな取り組み!
この取り組みは農家にとっても、障がい者が働いてくれることにより、担い手不足の解消や耕作放棄地の活用につながるというメリットがあります。このように双方が抱える課題を解決し、互いがウィンウィン(Win-Win)の関係にあるという部分が、農福連携という考え方が広まった重要なポイントといえるでしょう。
多様な作業が必要となる農業現場では、個々の特性に合った作業との出会いによって、障害者も農業の貴重な働き手となるとともに、農業を通じたスキルアップによる工賃の向上等を通じた生活の質の向上も実現することができます。
農家側のメリット
実際に農福連携に取り組んでいる農家は、どのようなメリットを感じているのでしょうか。ここでは日本基金が農福連携農家等(※1)と雇用された障がい者を対象に実施した「農福連携の効果と課題に関する調査結果」(2018年度)から、農家が感じたメリットをご紹介します。
まず、とても興味深いのは、障がい者を雇用したことで8割以上の農家が収益性に効果があったと回答していることです。(資料1) さらに、具体的な効果を問う質問では、障がい者を「人材として貴重な戦力」とした農家が7割以上。 そのほかの回答も合わせると、人員確保により時間に余裕が生まれ、新しいことにチャレンジするなど、障がい者の雇用が経営全体にさまざまな相乗効果をもたらしていることがうかがえます。(資料2)
一方で、障がい者とのコミュニケーションや障がいの程度の理解について、課題に感じている農家があることもわかりました。
(※1)障がい者を雇用又は福祉事業所等に農作業を委託している農家等
資料1 障がい者を受け入れることによる収益性向上に対する効果(回答者数105)



資料2 障がい者を受け入れることによる効果(回答者数109、複数回答あり)
| 障がい者を受け入れることによる効果 | 回答者数 | 回答者に占める割合 |
| 人材として貴重な戦力 | 83 | 76% |
| 農作業の労働力確保によって営業等の時間が増えた | 62 | 57% |
| 作業の見直しによる効率向上 | 46 | 42% |
| 経営規模の拡大 | 30 | 28% |
| 適期作業による品質の向上 | 27 | 25% |
| 人員の確保が容易になった | 24 | 22% |
| 新たな農作物の栽培にチャレンジできるようになった | 20 | 18% |
| 組織体制の見直しによる組織力向上 | 19 | 17% |
| 継続して農業を行っていく動機になった | 19 | 17% |
| 従業員の士気向上 | 17 | 16% |
| 新たな販路開拓等につながった | 12 | 11% |
| 人手の増加による作物の病気の早期発見、鳥獣害被害の防止 | 7 | 6% |
| 防除回数、防除にかかる経費の削減 | 6 | 6% |
| その他 | 12 | 11% |
調査によると、障がい者が担っている作業は「ほ場や畜舎等における作業」と答えた農家が8割以上を占めました。その内訳は下の表の通りです。
資料3 ほ場や畜舎等での具体的作業内容(回答者数 101)
| ほ場や畜舎等における作業内容 | 回答者数 | 回答者に占める割合 |
|---|---|---|
| 簡単な単純作業 | 75 | 74% |
| 体⼒を要する作業 | 58 | 57% |
| 経験を要する⼿作業 | 37 | 37% |
| 機械の運転 | 27 | 27% |
| その他 | 11 | 11% |
https://www.nipponkikin.com/survey-research.pdf
農福連携の取り組み例をご紹介!
グループ会社全体で農福連携に取り組んでいる、埼玉県の2法人をご紹介します!
ステップアップに合わせた就労サポート
特定非営利活動法人めぐみの里では、「“短期的な親切”よりも“人生を考えた思いやり”を」の理念に基づいた障がい者の就労支援に取り組んでいます。
同法人は、グループ企業であるアルファイノベーション株式会社から農産物の出荷調整作業や除草などの農場作業を受託し、障がい者に働く場を提供しています。障がい者の方々がそれぞれのステップに合わせて働けるようサポートしながら、働く喜びや充実感を感じられる場をつくっています。



農業と福祉の両方でキャリアアップ
特定非営利活動法人福祉ファーム里山では、関連会社の有限会社篠山堂と連携し、障がい者とともに農産物の生産から加工・販売を行っています。地域に根差して農福連携に取り組み、健常者と障がい者が手を取り合い、日々楽しく農業に取り組んでいます。
スタッフの仕事は農業と福祉部門に分かれ、農業比率が高い「野菜部」「加工観光部」では、農業経験がある、軽度障がい者とスタッフが一緒に作業し、反復しながら丁寧に教えます。福祉比率が高い「施設野菜部」では、障がい者が農業経験を通じて農業者として成長していくことを目的としており、見守りと懇切な指導が必要となります。
農福連携の環境を活かして、スタッフのみなさんは農業技術を習得しながら、福祉系の資格も取得してキャリアアップすることができます。



農福連携への支援制度
これまで障がい者を受け入れた経験がない企業にとって障がい者の雇用は、どのようなサポート体制を整えたらよいか、受け入れ準備費用はどのくらいかかるのか、勤務スケジュールはどう組み立てるかなど、ハードルが高く感じられるかもしれません。ここでは障がい者雇用に関する相談機関や国の支援策についてご紹介します。
ハローワーク
実は、労働相談窓口として身近なハローワークでは、障がい者雇用に関する相談も受け付けています。障がい者の雇用を考えている事業主には、雇用管理上の配慮やアドバイス、専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っています。
農業分野における障がい者就労マニュアル
・農業分野における障がい者就労マニュアル
農林水産省が発行するこのマニュアルには、障がい者就労の受け入れまでの流れが詳細に記載されています。上記URLから入手できます。
障がい者を雇用する場合の費用に対する助成制度
・障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
障がい者が安全に働きやすい職場環境を整えるための費用の一部を助成する制度です。・農山漁村振興交付金障がい者の雇用・就労などを目的とした農園を整備するための費用を一部助成します。
上記以外にも助成制度や各地方自治体による相談窓口もあります。制度を詳しく知りたい場合は、まずは最寄りのハローワークなど、身近な相談機関を利用することがおすすめです。
農福連携の今後の展開
農業、福祉、地域社会など幅広い分野にまたがって活躍する農福連携ですが、残念ながら現在の認知度はそれほど高くありません。また、継続的な勤務のための就労後のサポートや各地域社会の特色に合わせた就労支援など農業連携には今後の課題が数多く存在します。
農林水産省をはじめとした農福連携に取り組む組織は地域ごとの課題を地域内で共有・相談・解決できる場の創出や障害者等が働きやすいソフト・ハードの環境整備と課題を解決を試みています。
まとめ
農福連携は、「だれにとっても生きやすい社会の実現」「農業を持続可能なものにして食を守る」という視点で見ると、農業と福祉の分野だけにとどまらず、社会全体にも大きなメリットをもたらすと言えます。その取り組みは今後ますます加速することでしょう。 農業ジョブには、農福連携に取り組む農園の求人も掲載されています。福祉分野に興味がある方、福祉の資格やスキルを農業の分野で活かしてみたい方はぜひ「農福連携」「福祉」というキーワードなども入れて求人検索をしてみてくださいね。
農福連携に取り組む農園の求人一覧はこちら
よくある質問
農福連携とは何ですか?





農福連携は、農業と福祉が協力して行う活動のことです。具体的には、障がい者や高齢者が農業活動に参加することで、彼らの自立支援や社会参加を促す取り組みを指します。
農福連携を通じて得られるメリットは何ですか?





障がい者が働いてくれることにより、担い手不足の解消や耕作放棄地の活用につながるというメリットがあります。多様な作業が必要となる農業現場では、個々の特性に合った作業との出会いによって、障害者も農農業を通じたスキルアップによる工賃の向上等を通じた生活の質の向上も実現することができます。
農福連携の今後の展望はどうなっていますか?





農福連携は今後も拡大していくと期待されています。高齢化社会の進展に伴い、福祉と農業の連携がますます重要となり、多様な人々が地域社会に貢献できる環境づくりが進むでしょう。