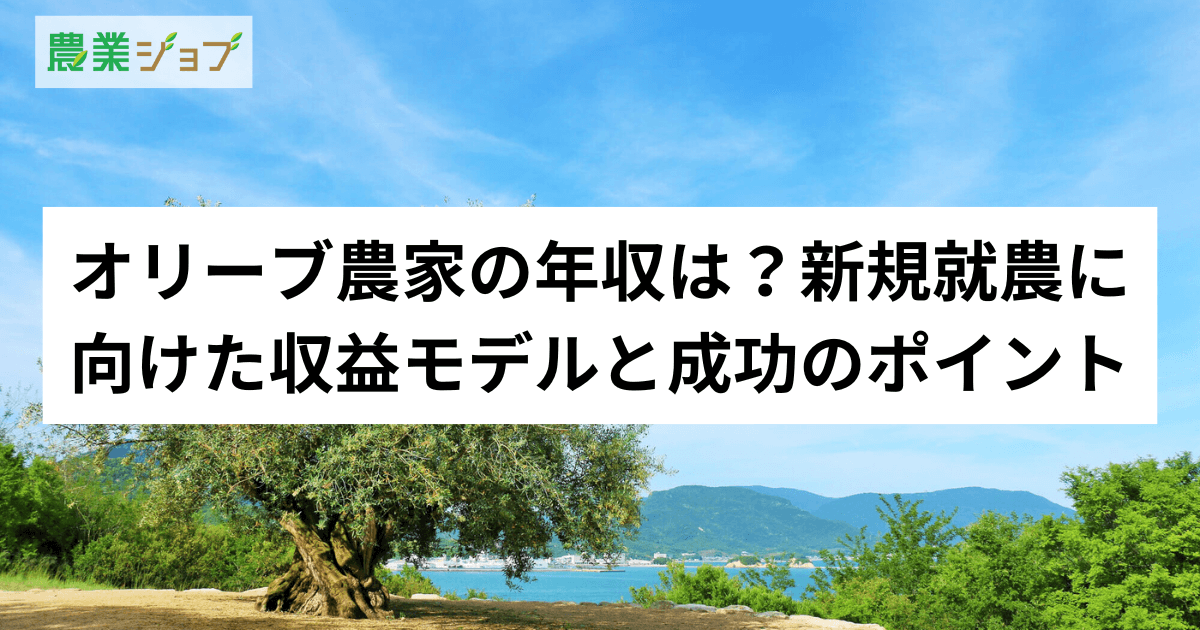農業に向いている人ってどんな人?
農業界で働きたいけれど、自分に適性があるのか分からない…。
「こんなにおいしいものがあるんだ!自分の手で作ってみたい!」という食への興味や、動物が好きだから、自然が好きだから、田舎に移住したいから、社会貢献性があるから等々、農業へ興味を持つ理由は人それぞれです。
農業の仕事
農業には色々な業種がある
「農業」と聞くと何を思い浮かべるでしょう?大半の方は野菜や畑、お米や田んぼが浮かぶと思いますが、野菜やお米、果物などを栽培する『耕種農業』のほか、酪農や養豚、養鶏などの『畜産農業』、農業資材会社や種苗メーカー、流通、販売など多岐に渡る『農業関連ビジネス』もあります。
農業の仕事は「農作業」だけじゃない
次に「農業の仕事」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。大半の方は種まき、収穫、トラクターの運転など、農産物や土に直接触る、いわゆる農作業が浮かぶと思います。これももちろん間違いではありませんが、農業の仕事は直接的な農作業だけではありません。
農業に向いている人の特徴
生き物(植物や動物)が好き
耕種農業は野菜やお米、果物や花など、畜産農業は牛や豚、鶏や馬などを大切に育てる仕事です。そのため、生き物が好きというのは必須条件です。
ものづくりが好き
農業は生き物を育てる仕事であることは一つ前にお伝えしましたが、さらに広い視点で見ると農業は「ものづくり」の仕事です。そのため、サービス業よりも何かを作ることが好きと言う人に適した仕事と言えるでしょう。
気配りができる
生き物が相手の仕事なので、扱う作物や動物の状態は毎日変化します。小さな変化の中に、感染症や連作障害、病害虫の繁殖などの大きなトラブルの芽が潜んでいる場合があります。そのため仕事中は常に気を配り、些細なことでもいつもと違う様子に早く気付いて対応できる人が大変重宝されますし、自分自身のやりがいにもつながります。
コツコツと地道に努力できる
ほとんどの業界では、がむしゃらに1年働くとそれなりに業界のノウハウが身に付きますが、農業は一年で一作しか回せない品目も多くあります。他業界に比べて経験を積むのに時間がかかるため、コツコツと地道な努力が必要となります。
忍耐力がある
機械やIT化が進んではいますが、体力を要する仕事も多く、忍耐強く業務ができなければ務まりません。
試行錯誤できる
他業界にも共通することですが、ただ言われたことをやるだけでなく、自分なりに試行錯誤して改善策を考えながら、生産性を向上させることが大切です。
データ管理など数字に抵抗が無い
農業もスマート農業やIoTといった単語を良く耳にするようになりました。 今までは熟練者の経験や勘で品質や収量を上げていましたが、現在は気温・水量・湿度・養分・日照時間などのデータを取って統計を出すことで病害虫への対策や、品質・収量の維持・向上の方法が可視化しやすくなりました。
コミュニケーションが取れる
農業の現場には幅広い年代の人がいます。熟練の農場長や長年お手伝いしてくれているパートさん、若手の社員・バイトから外国人の実習生まで、年齢・性別問わず色々な人が働いている職場です。そのため、どんな方とも意思疎通をしてスムーズに仕事を進めるためには、柔軟なコミュニケーションが必要となります。
全国の農業求人はこちら
農業に向いていない人の特徴
「自然が好き!」なだけ
農業を「自然の中でのびのびと爽やかに、マイペースに働ける仕事」と捉えている声がかなり聞かれます。もちろんそういう面もありますが、肉体的・精神的にキツイこともたくさんあります。
大雑把である
植物も動物も病気の初期症状は「葉の色が少し悪い」「果実の形が少々悪いものがある」「エサへの食いつきが悪い」といった程度の小さな変化ということもしばしば。しかし、その変化には感染力の強い病気、連作障害、病害虫の繁殖など大きなトラブルの原因が潜んでいる場合があります。そういった場合、初期段階での適切な病害虫の防除・病気の治療・隔離処置などが必要となります。
計画性が無い
農業は数ヶ月~数年先の収穫や出荷を目指して動く必要のある仕事です。耕種なら早生・中生・晩生など収穫できる時期に合わせて植え付けの段階で品種の選定が重要ですし、作物に合わせて土壌改良や施肥を行ない、植え付け後スムーズに作物が成長できるよう考える必要があります。 畜産なら通年で搾乳ができるよう出産計画を立てたり、仔牛・子豚・雛を出荷時に最適な大きさになるよう逆算して買い付けたり、エサの配合を変える必要があります。
臨機応変に対応できない
農業に計画性が大事なことは一つ前にお伝えしましたが、同時に、臨機応変な対応も必要になります。
一人で黙々と作業したい
「人間関係のしがらみから解放されて、1人で黙々と作業できそう」。
車の運転をしたくない
現在は自動車免許を持たない人が増えており、首都圏では車がなくても不自由なく生活できます。しかし、農業を仕事にするとなると話は別です。
一発逆転思考は危険!?
農業を始めたい方にお話を聞くと「農業は稼げるって何かで見たから、一発当てたいんだよね!」と言う方がちらほらいらっしゃいます。また、そのような方の大半は最初から独立or経営継承で自営したいと言います。
まとめ
極論ですが、農業に全く向いていない人はいないと思います。
向き・不向きを知ることも大事ですが、もっと大事なことは、自分の長所・短所を知るという意識です。
農業ジョブ エージェントに相談する