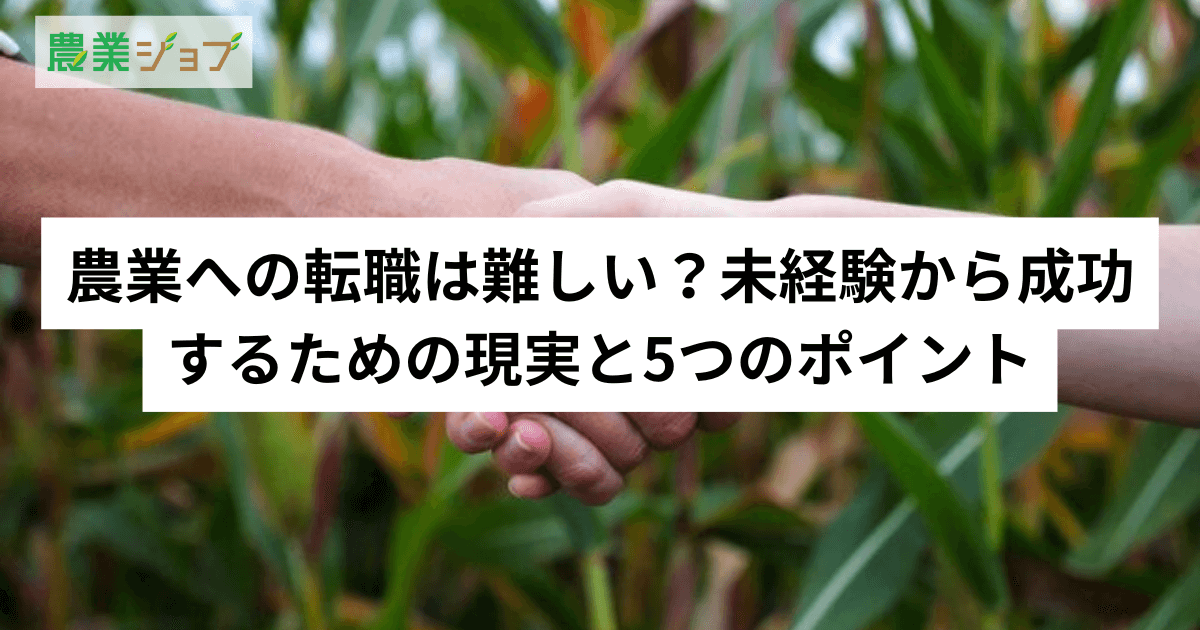世界農業遺産(GIAHS)とは?

世界農業遺産とは?
日本の伝統農業が新たなビジネスに
「世界農業遺産」という言葉をご存じでしょうか?
農業は人類の長い歴史の中で文化の形成や環境維持など、さまざまなものに影響を与えてきました。しかし、近年はロボット技術やICTといった新しい技術を駆使した農業も登場し、従来の農業を継承していくことが困難になってきています。 そうした中で、世界農業遺産は現在まで継承されてきた農村文化や田園風景といった伝統的な農業を未来に継承し、農村地域の復興・活性化につなげようとする取り組みを行っています。
「世界遺産との違いは?」「認定の基準は厳しい?」「認定されたらどんなメリットがあるの?」
当サイトではこのような質問にお答えします。
世界農業遺産とは?



世界農業遺産とは世界的に重要な伝統的農業(農林水産業)を営む地域をFAO(国際連合食糧農業機関)が認定する制度であり、「世界重要農業資産システム」とも訳されます。また世界農業遺産はGIAHS(Globally Important Agricultural Heritage Systems)ともよばれています。 世界農業遺産の認定により、農業や地域環境とともに育まれた文化や技術、景観、生物多様性などの「農林水産業システム」をトータル的に保全し、継承していくことを目指しています。
世界農業遺産の認定基準は厳しい?
①食料と生計の保障
農林水産業が地域の人々の所得や経済に貢献しているか
②農業生物多様性
農林水産業システムが生物多様性に貢献しているか
③地域の伝統的な知識システム
伝統的な技術がシステムに含まれているか
④文化、価値観と社会組織
農林水産業システムが生み出す文化的な面が含まれるか
⑤優れた景観と土地・水資源管理の特徴
優れた景観や土地・水資源の管理ができているか
世界農業遺産が創設された背景には、近代農業によって世界各地の環境問題や生物多様性、地域固有の文化・景観等が失われつつあるということがあります。 上記の5つの項目をはじめとした、農林水産業システムの維持・継承への取り組みがなされていることが求められます。
世界遺産との違い
世界遺産は有形の不動産が対象であり、厳正な保護が目的です。しかし世界農業遺産は農林水産業を営む地域が対象であり、保全はもちろん、持続的に活用することが目的です。世界遺産はユネスコ総会で採択されますが、世界農業遺産はFAOが認定します。また、日本での所轄官庁において世界農業遺産は農林水産省、世界遺産は文化庁となっています。 つまり世界遺産は現状を変えませんが、世界農業遺産は地域環境に適応し新たな技術を取り入れることが可能です。近代的な部分を取り入れ進化を続けながら、伝統的技術を残していけるのです。
世界農業遺産に認定されている日本の地域
世界で26ヶ国86地域、日本では15地域が認定されています(2023年11月10日時点)。
日本の認定地域一覧



資料:農林水産省「世界農業遺産とは」
日本で初めて認定されたのは?
2011年、「新潟県・トキと共生する佐渡の里山」と、「石川県・能登の里山里海」の2地域が日本で最初に認定されました。
世界農業遺産に認定されるメリット・デメリット



メリット
地域の農林水産業が世界的に認められることによって、地域の活性化や農業システム維持が推進されることにつながるでしょう。 また世界的に知名度が高まるため、農産物ブランドとしての付加価値が高まるなど、観光や農業の復興の面でも効果が期待できます。
デメリット
とりたててデメリットとして挙げられるものはありません。しかし世界農業遺産に認定されることにより維持・継承していくための補助金などがもらえるわけではない点には注意しましょう。
日本農業遺産と何が違う?



日本農業遺産とは?
「日本農業遺産」は世界的・国内的に重要な農林水産業システムを農林水産大臣が認定する制度です。社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域(農林水産業システム)を対象としています。 2017年3月に初めて選定が行われ、2023年1月時点で24地域が認定されています。



資料:農林水産省「世界農業遺産とは」
世界農業遺産との違い
世界農業遺産は伝統的な農業システムの保全に取り組んでいれば認定されます。一方で、日本農業遺産はすでに地域ぐるみで6次産業化の促進など、積極的に行われていることが基準となります また、世界農業遺産は、世界的に重要な農林水産業システムが認定されますが、日本農業遺産は世界的、そして国内的にも重要な農林水産業システムを農林水産大臣が認定します。



世界農業遺産の活用例
紹介地域① 能登の里山里海(石川県)



2011年に佐渡市とともに日本で最初に認定された石川県能登地域では認定後、奥能登の4農協が同一の基準を設けた特別栽培米、能登棚田米づくりに乗り出しました。ブランド化を図った結果、生産者の数、作付面積、出荷量ともに飛躍的に伸び、2013年に124トンだった能登棚田米の出荷量は、2016年には270トンにまで拡大しました。 また、奥能登で人気の農家民宿群「春蘭の里」に訪れる観光客も、国内・国外双方から増加しています。
紹介地域② クヌギ林とため池がつなぐ(大分県)



国東半島・宇佐地域では、世界農業遺産の認定をきっかけに乾しシイタケや米についてブランド認証制度を創設しました。認定された農業システムが持続的に保全・発展していくよう商品を地域ブランドとして発信する取り組みとなっています。 また、地域の人たちが中心になって世界農業遺産を巡るウォーキングコースの開発したり、県内金融機関と共同で60億円規模のファンドを造成し、その資金で次世代に継承するための教育を行ったりしています。
申請方法
①提案
候補地域は国や地域の政府、NGO、地元のコミュニティなどから提案されます。
②評価
FAOの専門家チームが提案を評価し、その地域の農業の歴史、文化的・環境的価値、持続可能性などを考慮して、世界農業遺産にふさわしいかどうかを判断します。
③認定
評価の結果、世界農業遺産として認定される場合、FAOによって正式に承認されます。
④保護と管理
認定後、その地域は適切な保護と管理が行われるようになります。地元のコミュニティや関係者が参加し、持続可能な農業と文化遺産の保護に取り組みます。
よくある質問
- 世界農業遺産の認定結果はどのくらいの期間で出る?
- 通常、申請から認定までの期間は数年を要することがあります。プロセスは詳細な審査と評価が伴うため、地域や申請内容によって異なります。
- 世界農業遺産に認定後の維持管理はどのように行われる?
- 認定後は地域が自主的に維持管理計画を立て、FAOのガイドラインに沿って実施されます。このガイドラインには環境の保全、伝統的な農業技術の維持、地域コミュニティの支援が含まれます。
- 地域コミュニティの反対がある場合、どのように対処する?
- 地域コミュニティの意見は世界農業遺産へ申請する上で重視される点であり、すべての関係者が合意する協議を重ねる必要があります。このような場合、FAOから対話と調整を促進するための支援を受けることができます。
まとめ
上記のように世界農業遺産に認定された地域では、農業遺産の保全や継承はもちろん、農産物のブランド化や知名度の向上、観光誘致、農業遺産を活用したビジネスなど、地域活性化における一定の成果を挙げています。
世界農業遺産の知名度はまだまだ低く、即時的な効果は認められないかもしれません。しかし、世界や国内で重要性が認められることで、地域に住む人が地域資源の大切さを再認識し、地域の活性化や遺産の持続性、次世代への継承に漸次的につながっていくはずです。このような試みは地域の自信や誇りの回復となるでしょう。