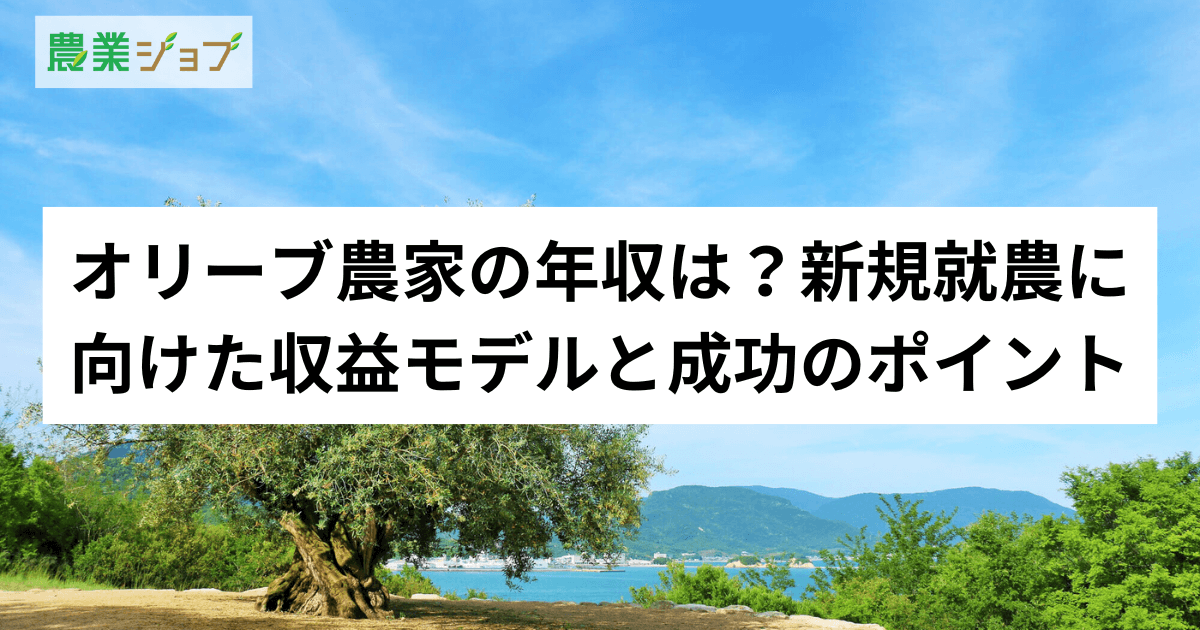果樹とは
概要(業種の基本情報)
現在、日本で生産されている果物は主要なものでも100種以上。大部分は年に一度の収穫に向けて、1年間かけて栽培します。
果樹生産は、季節ごとに旬の果物を生産し消費者に届けるのが仕事です。果樹に対し、一本一本の性質を見極め、水や肥料を与え、病気や害虫から守るという基本的な手入れを行います。日々変わる自然環境の中でも安定して果物を供給するため、年間を通じて絶え間なく作業が続きます。
産地毎のブランド化や、収穫した果物を加工品として販売する、いわゆる「6次産業化」に積極的に取り組んでいる生産者が多いのも、果樹生産の特徴です。
生産物例
収穫された果物は、流通を経て消費者に届けられます。一般的に、果物の流通は、卸売市場を経由する「市場流通」と卸売市場を経由しない「市場外流通」があります。果物の場合は市場流通が約8割を占めていますが、近年は直売やインターネット取引などの流通の多様化により、市場外流通が増加傾向にあります。また近年では、メイドインジャパンの品質を活かした、アジア諸国の富裕層に向けた輸出販路の開拓などの取り組みも活発化しています。
果樹生産の仕事
果樹の年間スケジュール(例)
【みかんの場合】
2~3月 剪定、施肥
3~4月 植え付け
6~7月 摘果(1回目)、施肥
8月 摘果(2回目)
9~10月 追肥、植え付け
10~12月 収穫
【りんごの場合】
1~3月 剪定・整枝
4月 肥料散布、苗木の植え付け
4~9月 農薬散布
5月 受粉、花摘み
5~7月 摘果
6~7月 袋かけ
9~11月 葉摘み、袋はぎ、収穫
果樹の1日の仕事の流れ(例)
06:30~07:30 起床・朝食
07:30~08:00 出勤
08:00~12:00 収穫
12:00~13:00 休憩(昼食)
13:00~17:00 収穫
17:00~19:00 選果・出荷準備
19:00~23:00 帰宅・夕食など
23:00~06:30 就寝
果樹にはこんな仕事がある
仕事の種類



収穫・出荷準備
熟した果物を収穫し、選果機や重量選別機にかけて選果。大きさや品質毎に分けて、箱詰めにして出荷します。果物によっては予冷や追熟を行い、食べごろに調整してから出荷します



花摘み・受粉
りんごやももなどの場合は、花が咲く時期に花摘みを行います。一番最初に咲いた花を残し、それ以外を摘み取るこの作業は、花が咲いてから散るまでの10日間程に集中して行います。自家受粉をしない果物の場合は、人の手によって受粉作業を行います。受粉作業用の機械を使う場合と、マメコバチ等の昆虫を使う場合があります。



剪定
日当たりや風通しをよくし、実のなる枝が充分な養分を得られるように、枝を切り落としていきます。発芽前の冬や春に行うことが多いですが、樹形の調整のために夏季に行う場合もあります。剪定には、剪定バサミやのこぎりを使います。1本1本作業するため、非常に根気のいる仕事ですが、果実の収穫量や品質に影響する大切な作業です。



その他
事業体によっては、加工品の商品企画、PR活動、イベントでの販促活動などの仕事があることもあります。
果樹の仕事のやりがい・働く魅力とは?



一年を通してじっくりと栽培に取り組むことができる
果物の栽培には一年間かかるため、じっくりと取り組むことができます。同じ作業を黙々とこなす根気強さが必要ですが、その分特定の果樹の栽培技術をしっかりと身につけることができます。



お客様からの「おいしい」の声
フルーツ狩りや加工品の生産・販売を行っている果樹園も多いため、消費者との接点が多いのが果樹の仕事の特徴です。
約1年をかけて育て上げた果物は果樹生産者の努力の結晶。 お客さんから「おいしい」という声が届いた時には、大きな喜びを感じることができるでしょう



自然の中で身体を動かして働く
果樹とは文字通り「樹」になる果物を生産・収穫する仕事。剪定や収穫のために高い所に登ったり、みかん生産の場合は収穫したコンテナを持って山肌を往復するなど、体力も必要とされますが、それだけに、自然の中で働いている充実感が得られます。
果樹栽培では第6次産業化が拡大中
六次産業化とは、第一次産業(農業、漁業、林業)を基盤に、第二次産業(加工)や第三次産業(販売、観光など)を組み合わせて、付加価値を高める取り組みを指します。
近年、果樹栽培を行う農家が生産物をジュースやジャムに加工したり、に農場の一部を観光農園として経営したりなどして収入源を増やす農家が増えてきています。
果樹栽培の求人一覧はこちら
果樹のQ&A
- 果樹栽培とは?
- 果樹生産は、季節ごとに旬の果物を生産し消費者に届けるのが仕事です。果樹に対し、一本一本の性質を見極め、水や肥料を与え、病気や害虫から守るという基本的な手入れを行います。日々変わる自然環境の中でも安定して果物を供給するため、年間を通じて絶え間なく作業が続きます。
- どんな人が向いていますか
- 果樹の仕事は、1年間という長いスパンで、また、1つの作業にじっくり取り組むことが多いため、根気のある人が向いています。また、栽培する品目によっては花摘みや受粉などの細かい作業があるため、手先の器用な方も向いていると言えるでしょう。
- どんなキャリアが積めますか?
- まずは農業法人への就職や研修などで、生産する果物の栽培技術を一通り覚える事が基本です。一年に一度しか収穫できない果樹の場合、予期せぬ病気や天候に対応する技術や知識の習得には比較的長い年月が必要となります。そのため、 独立を目指す場合などは、野菜などの農産物と比べると必要な研修期間は長くなります。
- 長期休暇はとれますか?
- 果樹の生産は一年サイクルで行うため農繁期と農閑期があり、時期によってはまとまった休みを取ることも可能です。農園によっては、休暇制度を用意しているところもあります。ただし、農繁期(収穫期)になると収穫はもちろん選果や出荷作業もこなさなければならないため、休み返上で働く事もあります。
- 体力面が心配。女性でもできますか?
- 身体を動かす仕事になるため、ある程度の体力は必要ですが、女性でも働くことは可能です。
- 未経験でも働けますか?
- ほとんどの農園では基本的な仕事から栽培技術まで一から教えてもらえるため、未経験でも問題ありません。加工品の製造・販売などを行っている農園であれば、企画、営業、販売など、農業以外の経験が活かされるケースもあります。