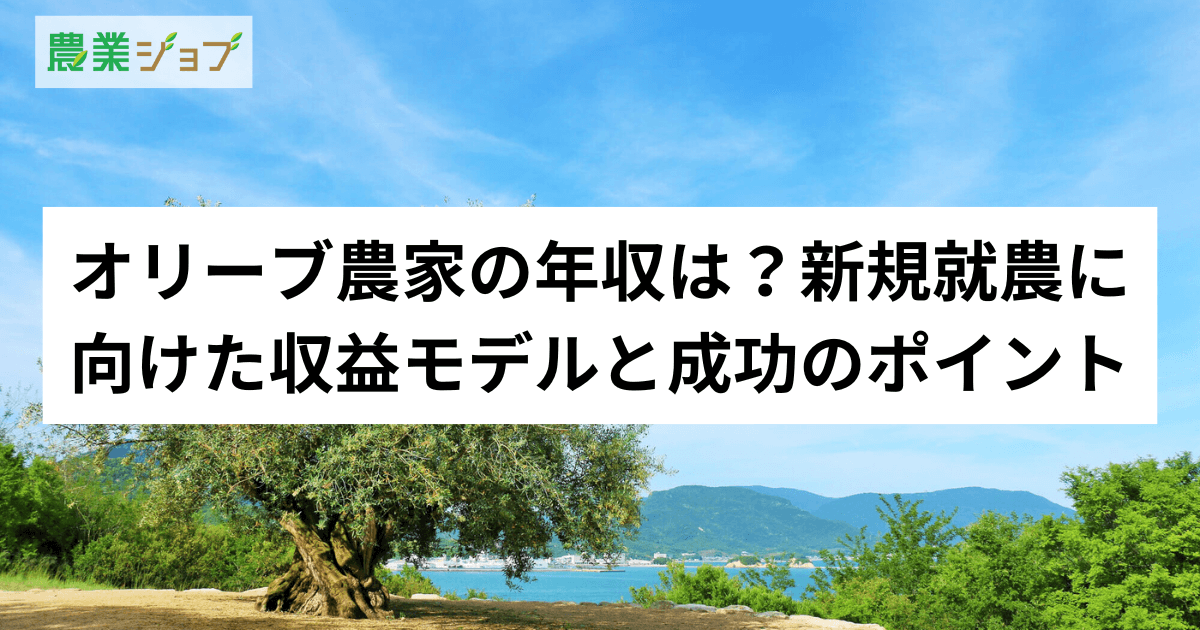世界的に類を見ない
農業界の大きな協同組合
日本人なら誰でも知っているけれど、でも一体どんなことをしている組織なのか意外とわかっていないJA(ジェイエー)について今回は取り上げたいと思います。
JAという組織は、営農指導はもちろんのこと、金融、共済、新聞・出版事業など幅広い事業を担うとても大きな協同組合です。
それでは今から解説していきます。
JAの歴史
JAは、『農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会を築くことを目的に組織された協同組合』です。JA(ジェイエー)は、「農業協同組合」の英語表記「Japan Agricultural Cooperatives」の頭文字をとってつけられたニックネームです。他に「農協」という通称もよく耳にしますね。
まずJAがどのような経緯で作られたのか紐解いていきましょう。
設立されたきっかけ
日本における農業協同組合は、江戸時代頃にできたと言われています。明治以後には近代化され、「産業組合」や「帝国農会」といった協同組合が組織されます。太平洋戦争時には、農業生産物を一元的に集約する目的で「農業会」という統制団体に改組されました。
そして、太平洋戦争後の1948年、既存の「農業会」を改組する形で今の農協(JA)が生まれました。もともと、GHQは戦後の農地改革の一環として、欧米型の農業協同組合(行政から独立し、自主的に組織できる)を作ろうとしていたそうですが、当時は深刻な食糧難だったため、行政が食料を統制・管理する形が採用されました。
1992年4月からは、「農協マーク」に代わり、「JA」の名称や「JAマーク」を使い始めました(図1)。『相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会を築くことを目的に組織された協同組合』として、今日のJAはあります。
 図1
図1
協同組合と株式会社の違い
協同組合とはどんな法的にどんな組織なのでしょう?それを理解するために株式会社と比較してみます(図2)。


 図2
図2
株式会社と協同組合の一番の違いは、利潤の追求ではなく、協同組合はあくまで組合員の生活を守り向上させることが目的です。そのため、協同組合は組合員1人につき1票を持てます。つまり、生産力や資本力に関係なく組合員は平等に組合に対して権利を持てるわけです。
一方、株式会社は、利潤を追求し、その利潤を株主に配当し、株をより多く持っている人が影響力を持つことができます。
組合員と職員
JAの組合員には農家以外の方でもなることができます。
「正組合員」は、農業を仕事にしている団体(農家や農業法人)です。耕作面積や農業従事日数などから正組合員になるための具体的な基準を定めています。
一方、農業以外の仕事をしている人が、地元のJAに出資金を払い込み、その他の手続きをすることで「准組合員」として加入することができます。
では、「正組合員」と「准組合員」の違いはなんでしょうか?
「正組合員」は総会での議決権や役員の選挙権などJAの運営に関与することができますが、「准組合員」はできません。この准組合員制度は、他の生活協同組合にはなく、JA独自のものです。
また、制約はありますが、正組合員や准組合員だけでなく、一般の人もJAのサービスを一部で利用することができます。
加えて、協同組合には、組合員の他に職員がいます。JAでは、総会で事業方針を決め、さらに代表者(組合長)を選び、その指示のもと、組合員の業務代行人として職員が組合の業務を行います。
JA支援のもと掲載している求人はこちら
JAグループ
JAは、営農指導はもちろんのこと、生産資材・生活資材の共同購入や農畜産物の共同販売などの農業関連の業務を担います。
あるいは、貯金の受け入れ、農業生産資金や生活資金の貸し付け、農業生産や生活に必要な共同利用施設の設置、あるいは万一の場合に備える共済等、広範囲の事業で組合員を支援しています。
組合員のために行っている共同事業が非常に多く、組合員も多いため、効率的かつパワフルな事業展開をはかるため、多くの地域JAを束ねる都道府県段階のJA組織、それらをさらに束ねる全国段階のJA組織が作られました(図3)。


 図3 グループ組織図
図3 グループ組織図
代表機能「JA全中」
「JA組合員+全国のJA組織」の共通意思の結集を図るのが、「JA全中(一般社団法人 全国農業協同組合中央会)」です。組織・事業の枠を越えて連帯するJAグループの代表として運営されています。都道府県段階でまとめているのが「JA都道府県中央会」でさらにその全国まとめ役が「JA全中」ということです。
JA全中は、1954年に農業協同組合法上の特別認可法人として設立され、65年にわたって活動してきましたが、同法の改正を受け、2019年に組織形態を一般社団法人に変更しました。
総合調整や経営相談を担い、地域・事業の枠を越えてJAグループの総合力を発揮します。一般企業で言うホールディングスのようなイメージです。
また、組合員に向けて、農業への取り組み方針を示したり、国の施策などの情報提供を行ったりしています。政策提言をまとめて農水省などに提出し、自分たちの意向を政策に反映させる仕事もしています。
経済事業「JA全農」
経済事業を担うのはJA全農(全国農業協同組合連合会)です。1948年、全国農業会の改組に伴い、全販連(全国販売農業協同組合連合会)、全購連(全国購買農業協同組合連合会)を設立。1972年に全販連と全購連が合併し、全農(全国農業協同組合連合会)が設立しました。
JA全農の経済事業は、主に「販売事業」と「購買事業」です。
(1)販売事業
組合員が生産した農畜産物をJAが集荷して販売することを「販売事業」と呼んでいます。その規模は、例えば青果物は、生産者の農業産出額のうち半分以上がJAに出荷され、全農にはその80%以上が経由して、卸売会社などを通じて消費者に渡ります。全農は日本の農作物流通のキーマンであることがわかります(図4)。


 図4 農産物の流通(例:青果物流通の概要)
図4 農産物の流通(例:青果物流通の概要)
※「生産者のJA利用率」および「JAの連合会利用率」はH25年度の数値。
また、JAの販売事業は「共同販売」で行うため、「共販」とも呼ばれます。農畜産物の数量や品質を均一にし、共同で販売することで、市場で良い条件での販売を狙っています(図5)。



一方で、価格はJAが決めるので、農家(生産者)が自分で作った農産物をいくらで売るのかを自由に価格設定できないのも事実です。
その中で、全農は改革も進めています。その一環に、『全農営業開発部』や『全農グループMD部会』(事務局:営業開発部MD企画課)などのバリューチェーンの構築を目指す部署の立ち上げがあります。
外食企業や食品メーカーなどの企業と生産者を繋ぎ、細かいニーズに合わせた商品開発するなど、これまでのサプライチェーンの枠を超えた新しい価値を作ろうとしています。
(2)購買事業
購買事業は、大きく2つに分かれます。ひとつは、肥料、農薬、飼料、農機具等、組合員の営農活動に必要な材料の供給を行う生産資材購買です。もうひとつは、食品、日用雑貨用品、耐久消費財等、組合員の生活に必要な物資を供給する生活資材購買です。スケールメリットを生かしてメーカーと交渉し、低価格・安全・良質の資材を組合員に提供しています(図6)。
2015年度の購買事業の取扱高は、JAで2兆6,079億円、JA経済連で8,962億円、JA全農で2兆2,226億円となっており、大きなお金が動いています(※1)。
※1 出典:JAグループwebサイト(https://org.ja-group.jp/about/group/economy)


 図6 共同購入のしくみ
図6 共同購入のしくみ
JA全農の都道府県版というべき組合として、「経済農業協同組合連合会(JA経済連)」と「県JA」があります。これまで32都府県にあったJA経済連は、統合してJA全農の都府県本部となりました。現在では、8道県(北海道(ホクレン)、静岡、愛知、福井、和歌山、熊本、宮崎、鹿児島)にJA経済連があります。また、地域のJA同士の合併が進み、県域で経済事業を展開する県JAがあるのは、奈良、島根、山口、香川、高知、佐賀、沖縄の7県です(2019年7月現在)(図7)。


 図7 JAグループ組織図(経済事業)
図7 JAグループ組織図(経済事業)
※農協(JA、県JA)の数は2019年7月現在
「JAバンク」「JA共済」「厚生事業」
「JAバンク」は、JA・JA信連・農林中央金庫の会員で構成され、地域ごとのニーズに応えながら、全国に⺠間最大級の店舗網を展開し、さまざまな金融サービスを提供しています。その規模はとてつもなく大きいです。例えば、貯金残高を日本の3大メガバンクと比較すると、
・三菱UFJ銀行 1,53兆円(※2)
・みずほ銀行 1,19兆円(※3)
・三井住友銀行 1,16兆円(※4)
・JAバンク 1,03兆円(※5)
(2019年3月末)
※2 出典:三菱UFJファイナンシャルグループ財務情報
※3 出典:みずほファイナンシャルグループ決算時系列データ
※4 出典:三井住友ファイナンシャルグループ決算資料
※5 出典:JAグループwebサイト(https://www.jabank.org/about/jyokyo/)
となっており、いかにJAバンクが巨大かをわかってもらえるのではないでしょうか。
JAは農家のための組織ですから、JAバンクでも農家が優遇されますが、制約はあるものの一般の人も口座を作ることができます。
「JA共済」は、相互扶助を事業理念として、組合員・利用者と共済契約を締結することによって、「ひと・いえ・くるまの総合保障」(生命と損害の両分野の保障)を提供しています。
また、JAグループは医療の確保も目指し、健康増進活動の促進、医療の提供、高齢化の対応等、地域におけるニーズに対応しながら積極的に取り組んでいます。JAグループはこれらの事業を「厚生事業」と呼んでいます。
その他(旅行、新聞・出版、相続・事業承継支援対策など)
JAグループは他にも相続・事業承継支援対策、旅行事業、新聞・出版事業など、組合員をあらゆる角度から支援しています。また、企業や行政、海外とのネットワークも積極的に構築しています。
JAの土台となる指導事業
JAの行う指導事業とは、「営農指導」と「生活指導」に大きく2つに分けられます。
営農指導
JAは、農業の技術・経営指導、農畜産物市場の情報提供、新しい作物や技術の導入など、組合員の営農支援のための活動を行っています(図8)。


 図8 農業経営⽀援(イメージ)
図8 農業経営⽀援(イメージ)
また、地域農業戦略の策定、農地利用調整、最近では農家の育成・確保、環境保全型農業の推進などにも力を入れています。
その中で、農家の相談相手になり、指導を行っているのが、営農指導員と呼ばれる人たちです。JAと農家を結ぶパイプとして重要な役割を果たしています。
最近では、農家の要望もますます多様になってきています。JAは、その対応が可能な専門性の高い営農指導や、個別事業提案を担える人材の育成にも力を入れています。
その一環として、2008年から全農は、「TAC(Team for Agricultural Coordination)」を設置しました。このTACは、将来にわたり地域農業の中核となりうる担い手(経営者)を対象に、その意⾒・要望をJAにつなぐ専⾨の職員のことです。
現在では、営農指導員やTACが中⼼となり、多くのJAがそれぞれの⽣産者の経営に合わせて⽣産者を総合的にサポートする「農業経営⽀援(農業経営コンサルティング)」の取り組みも進めています。
生活指導
貯金や貸付、死亡や病気、火災、自然災害など不測の事故が生じた場合に備える各種共済なども提供し、組合員が安心して事業に取り組める環境を整えています。
最近では、組合員や地域住民の生活様式やニーズが多様化してきたため、そのくらしの各分野を支援する「くらしの活動」も積極的に行なっています。
この「くらしの活動」は、組合員だけでなく、地域住⺠も一緒に参加でき、⾷農教育、都市農村交流、⾼齢者⽣活⽀援、助け合い活動、⼥性⼤学などがあります。
このような活動を通じて、農業振興による地域の雇用や所得への貢献、生活インフラ機能の発揮、地域コミュニティの形成等による「地域の活性化」も目指しています。
その他(販売事業、生産資材開発・普及など)
組合員が生産した農作物を集めて、卸売業者や小売業者に卸したり、肥料や農薬、飼料、農機といった生産資材を組合員に提供することもJAは担っています。
JAの販売事業のうち「共同販売」することを「共販」と呼ぶのですが、これにより農畜産物の数量がまとまり、一定レベルの品質を均一にそろえることで、スケールメリットを狙っています。
私たちみんなに身近なJA
お住まいの地域に身近なJA〇〇町のような看板の建物、いわゆる近所のJAがあると思います。こういったJAグループの最小単位の組織を単位農協(単協)と呼んでいます。
単協の仕事と私たちとの結びつき
全国各地に必ず存在する近所のJA(単協)は、どんなことをしているんでしょうか。
JAえひめ中央の部署を例に取り上げてみてみましょう。
■営農経済部門
・営農部
営農部は、生産指導と営農振興などを行なっています。
・販売部
販売部は、組合員が生産する農産物の集荷・荷造り・販売を行っています。
・直販部
太陽市・アンテナショップひなた・えひめ中央おひさま食堂や、えひめ中央ひなたCAFÉの運営を行っています。
・購買部
→資材課
農業生産に必要な肥料、農薬、資材を管内の約40店舗で販売し、食品、日用雑貨、家電等あらゆる商品の取り扱いもしています。
→旅行センター
全国を網羅するNツアーと提携し、ツアー計画立案からチケット発券まで丁寧に対応しています。
→燃料課
セルフSS(サービスステーション)を中心に、各SSでガソリンや灯油、軽油などの販売を行っています。また、燃料センターはLPガスやガス器具の販売を行っています。
→農機自動車課
自動車、農機具の販売と車検、修理及び関連部品や資材を取り扱っています。
・加工部
加工部では、伊予柑をはじめ紅まどんな・せとか・甘平等を使用したカップゼリーやゼリー飲料等の製品、栗を中心とした缶詰製品、味噌醤油等の醸造品の製造・販売を行っています。
■金融部門
・金融部
金融商品の提供と金融サービスの充実に取組んでいます。
・審査管理部
→査管理部
各種ローン・農業資金の適切な運用などをしています。
・共済部
一人ひとりの生活スタイルに応じた保障プランニングを行う相談・提案型保障設計サービスの向上を図っています。
・本店営業部
貯金、融資、共済事業をまとめた営業に特化した部署です。
■管理部門
・総合企画室
→企画課
組合の事業計画並びに中・長期経営計画を策定し、その進捗管理を行っています。また、広報誌の発行やホームページ・SNSの更新管理を行うなど広報活動も行っています。
・電算課
経済管理業務システムの安定稼働に取り組むとともに、事務の合理化・効率化を進めるためのシステム改善を行っています。また、組合員・利用者のニーズにマッチしたシステム構築およびIT技術導入等の提案とシステム改修に取り組んでいます。
・総務部
→総務課
事業管理費等の削減および遊休不稼働資産の有効活用等に努めています。
→人事教育課
職場環境の改善および職員の資質向上に努めています。
→経理課
正確かつ迅速な部門別損益分析と事務処理対応を行います。
→福祉課
居宅介護支援、訪問介護および通所介護の三つの介護保険事業を実施しています。
■監査室
当JAでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置しています。経営者が組合経営上のリスクに対応して整備・運用する内部統制システムの有効性を検証・評価し、課題の指摘や改善の提言を行っています。
■リスク統括室
内部統制の構築・運用状況を統括管理して業務の適正性を確保すると共に、総体的リスク量や自己資本規制の経営リスク、投資に対する牽制機能を発揮したリスク管理など、損失の危険の管理体制を整備・対応しています。
日本には四季があり、農業にも産地があり、そして地域の抱える生活の課題があります。単協は、そういった各地の実情に合わせて、柔軟にJAのサービスを展開する最も身近な窓口として機能しています。
ファーマーズマーケット
JAグループは時代とともに、柔軟な農業の運営をしてきました。
例えば、今、JAグループが直接、生協等の消費者組織や食料品を中心とした生活用品を販売するAコープ(スーパーマーケット)を展開しているほか、インターネットを介した商品配送サービス「JAくらしの宅配便」、定期的に食材等を家庭に届ける「食材宅配」などの事業を展開しています。
単協も、それに呼応する形で、農産物直売施設等、独自の店舗を設置するところや、宅配便等で消費者に直接配送するなど、独自色を強めています。
象徴的なのが「ファーマーズマーケット」です。地域に住む人たちに地元産の新鮮な農畜産物を供給しています。
単協独自の試み
今回取り上げたJAえひめ中央は、JA直営複合施設「みなとまち まってる」を2019年4月にオープンしました。
県内産農産物を使った料理が味わえるJA直営の食堂やカフェ、金融・共済・ローン窓口や保育園、ベーカリーなども入った施設です。
あるいは、静岡県浜松市にあるJAみっかびは、特産品の三ヶ日みかんの生産に特化し、ITを使った営農指導やインターネットを使った販売戦略など意欲的な活動をしています。
そこにあるのは、農業をベースにしながら、多角的に事業を展開するスケールの大きな組織の姿です。
まとめ



JAとは、国民にとって一番大事な食料という分野、つまり日本の農業をフィールドにした最も大きな組織です。
自分が農家でなくても、知らないところでJAと接点を持っている方も多いのではないでしょうか。例えば、住む地域に単協があることを知らない方でも、ファーマーズマーケットで買い物をしたことがあるかもしれません。
またこれから農業をしたい!農家になりたい!そう真剣に考えて行動を起こす方々を全面的に支援する役割も果たしています。地域の役場や農業委員会と一緒になって、新規独立就農を目指す研修生のサポートをしています。
この日本という国において、JAという組織が担っている役割のスケールの大きさだけでも理解していただけたでしょうか。これからも時代に合わせて、歴史あるJAという組織のカタチは少しずつ変化していくことでしょう。