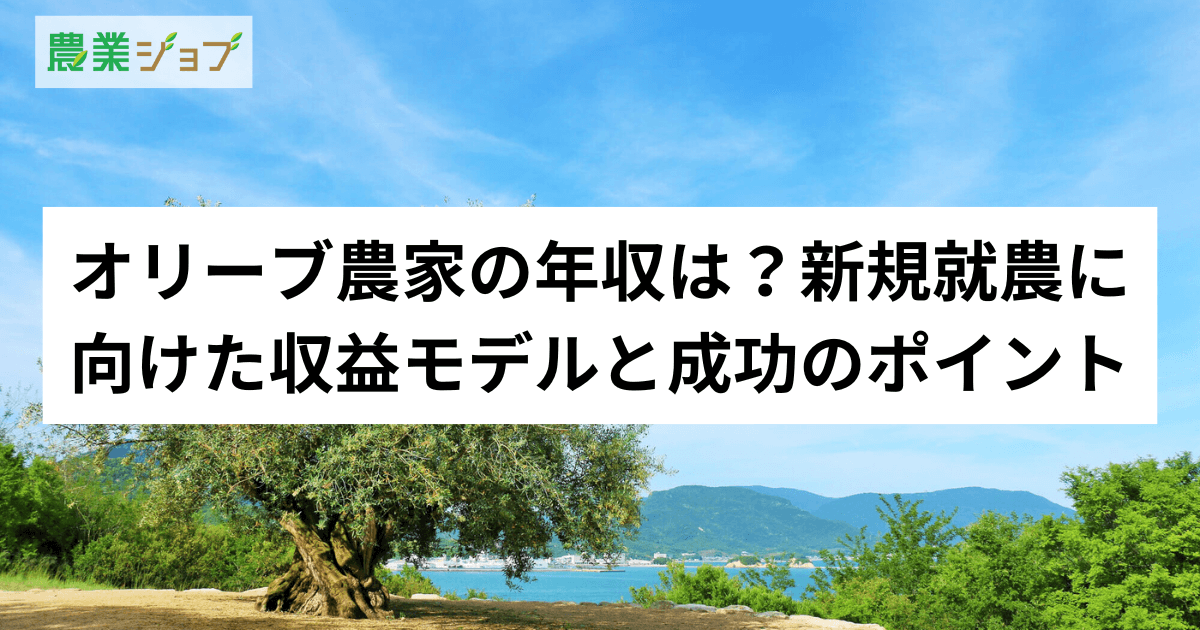農業に就職!基本の「き」をご紹介
こんなはずじゃなかった…!
を防ぐキャリアプランの作り方
就農パターンを決めよう
一般企業では、会社員になる/起業する/家業を継ぐなどの就業パターンがあります。農業でも同様に、独立志向なのかどうかで就職先選びのポイントが異なります。まずは自分が目指す就農パターンを考えてみましょう。 主な就農パターンは次の4つです。
農業法人に就職する
将来的な独立は強く意識せずに、従業員として農業法人で働くパターンです。キャリアアップでは、農場長、生産や経営の幹部や社長となることがあります。
農業法人に就職した後、独立する
一旦は農業法人で勤務して経験を積み、その後に独立するパターンです。就職活動時には、独立支援の有無や、習得したい技術や知識の有無など、独立を意識した視点で農業法人を選ぶことができます。
既存農家を経営継承する
後継者のいない農家の経営を引き継ぐパターンです。移譲希望の農家から技術や経営管理のノウハウを教わり、販路・農地・機械施設等の経営資産を継承することができます。地域や作目は移譲希望者の状況により限られます。
農業法人に就職せず、自分で農業を始める
自分がやりたい経営を自由に目指すパターンです。起業することと同じで、始める前と後にそれぞれ多くのハードルがあります。農業経営像を具体的に描いて、就農候補地でも直接情報を集めたり人間関係を構築したりといったことが必要です。また[技術やノウハウ/資金/農地/機械や施設/販路]といった最低限の5つの生産資源の獲得が必須です。
業種を選ぼう
農業にも多くの業種があります。まずはどのような業種があるのかを把握して、自分の興味に合った業種を選びましょう。
経営作物を調べよう
各業種が生産する作物は様々あり、それぞれの品種も多様です。例えばトマトの品種は200種以上。消費者として野菜や肉を知っていても、生産者の目線で経営作物についてあらためて調べてみると良いでしょう。野菜の場合は例えば種苗メーカーのWEBサイトなどで調べることで、食べる側から作る側へ視点を移すことができます。農業未経験者が最初から難しい文献を読む必要はありませんが、例えば次に挙げるような基本的な情報を押さえると、就職を考える際に役立ちます。
主な生産地
気になる作物や品種がある場合、それらの主な生産地を調べてみましょう。それらを作りたい場合、生産が盛んな地域を対象に就職活動することが有効な場合があります。また住みたい地域も決まっている場合には、その地域で作りたい作物を作れるのか、作っている就職先があるのかも見ていきます。
一般的な生産サイクル
作物によって生産のサイクルは異なります。そのサイクル次第で働き方が変わってくることがあります。通年で安定生産されるものであれば働き方の季節変動も比較的小さくなります。季節毎でそれぞれ作業が大きく異なったり、作業ピークがある場合には、勤務の内容・時間帯・量・場所などが大きく変化することもあります。希望の働き方と大きなズレが生じることが無いかどうか、あらかじめ一般的な生産サイクルを把握しておくと良いでしょう。
一般的な販売先
生産物の流通についても調べてみましょう。生産したものが消費者に届くまでにはどのような流れになっているでしょうか。気になる経営作物については一般的な流通を把握すると、その中で自分が担う範囲をイメージしやすくなります。例えば肉牛の場合は、大きく4つの流通(生体流通、枝肉流通、部分肉流通、精肉流通)と2つの市場(家畜市場、食肉卸売市場)があります。食肉センターや加工業者など様々な関係者がこの流れに関わって、肉牛が最終的に「お肉」として消費者に届きます。中には生産に加えて加工と販売までも生産者自らが行う「6次産業化」を行っている場合もあります。
農業法人を探そう
未経験者のキャリアプランとして代表的なのは、農業法人への就職です。直接新規就農するパターンもありますが、ここではまず就職活動のポイントをご案内します。就職先を選ぶ際には、仕事内容や給与以外にもチェックしておくべきポイントがあります。人によって重視するポイントは異なりますが、まずは以下の内容を参考にして自分の判断基準について考えてみましょう。
法人形態
農業法人とは、法人形態で農業を営む法人の総称です。農業法人は大きく2タイプに分類されます。営利行為を行うことを目的とする「会社法人」と、組合員の協同利益増進を図る「農事組合法人」です。その中で、“農業経営を行うために農地を取得できる法人”農業法人を「農地所有適格法人」とと言います。「農地所有適格法人」となることができるのは、「会社法人」の4形態(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社)と「農事組合法人」の中で、要件を満たした法人です。将来独立を目指す場合には、自分が目指す法人形態を選択すると、経営の参考にもなりやすいでしょう。農業法人に対して、個人事業主である家族農業経営体は約150万あります。個人事業の場合は、組織が小さいことも多く、代表者の右腕として様々な活躍を期待されることが多いようです。やりたいことや意見があれば積極的に取り入れてもらえることもあり、個人事業ならではの魅力もあります。
組織規模
規模の大きい法人では、一般的に研修体制がより充実しています。また設備面や制度面などでも先進的な経営をしていることがあります。一方で規模の小さい法人では、自分を育ててもらうだけでなく、組織を一緒に育てていくような心構えが求められることが多いようです。農業法人の組織規模を選ぶのは、一般企業就職で大企業志向なのかベンチャー志向なのか、にも近いと言えるでしょう。農業での就職の場合でも、組織の規模感をあらためて意識して法人を見てみましょう。将来独立を目指す場合でも、組織の成長フェーズに応じて得られる知識や経験は異なります。すでに成長した組織で学ぶか、小組織で幅広く実戦経験を積むか、あらためてプランを考えてみると良いでしょう。
勤務地
転勤のある農業法人は稀です。また将来独立する場合でも、経験を積んだ地域以外からの独立は困難です。そのため農業では一般的に、就職する勤務地がその後の生活地となることがほとんどです。農業をしたいと思ったら、どの地域に根ざすのかについても覚悟を持って決めることが求められます。住みたい場所を基準にして業種や法人を選ぶ場合もあれば、逆に業種等から決めて、それらが盛んな地域を選ぶ場合もあります。気になる地域がある場合には、その地域特性についてもあらためてよく調べてみて、仕事も暮らしも十分にイメージできるように準備しましょう。将来独立を目指す場合には、どこで独立するのかも就職段階で計画して、就職活動の考慮に入れるのが好ましいです。
独立支援
農業法人に就職して経験を積んでも、将来の独立時には多くの生産資源が必要となります。それらの支援に力を入れている農業法人もあり、独立希望の場合には支援の有無が有力な決め手となることがあります。例えば独立時の設備や資金や土地を用意してくれたり、生産物を買い取ってくれたり、などの支援があります。独立後もパートナーとして心強い存在となります。独立支援を利用した独立実績がある場合には、その独立者も訪問してみると、より将来像をイメージしやすくなるでしょう。
複合事業
生産以外に、加工や販売等を一貫して手がける「6次産業化」を行っている農業法人があります。小売販売や観光事業など、生産以外の幅広い分野に興味がある場合にはそれらに取り組んでいる、またはこれから取り組もうとしている農業法人に就職することも考えられるでしょう。実際に商品を試したり、観光体験をしたりすることも重要です。実際に就職すると、他の農業法人の顧客になることは少なくなる場合があるので、就職活動の段階で積極的に比較体験しておくと、就職後の参考にもなります。
経営継承
後継者がいない農家、とは後継する魅力が無い農家とは限りません。もしかすると地域の人口が減っていたり、需要の小さい生産物を作っているような場合はあるかもしれませんが、移譲者とあなたの工夫次第で新たな価値を生み出していく、という挑戦をすることができます。研修を受けられるだけでなく、土地や設備などの資産を継承できるため、新しいチャレンジにも比較的速いスタートを切れる可能性もあります。また移譲者の中には品評会などで高評価を得るような優良農家もいるので、将来的に自分で経営をしたい場合には、まずは選択肢に入れて検討してみることがおすすめです。農業法人ではなく個人事業の農家である場合もあります。
自分の価値観を知ろう
就職活動は求人者と求職者のマッチングのプロセスです。就職先が自分にマッチするかどうかを判断するためには、就職先だけでなく自分についても知る必要があります。例えばみんなに人気の農業法人ならば必ずあなたにも最適、ということはありません。一般企業への就職活動者が行う「自己分析」は農業でも有効です。「こんなはずじゃなかった」とマッチングに失敗してしまう可能性をより小さくするためにも、きちんと時間をとってあらためて自分について考えましょう。「自己分析って何?」という方は、以下のポイントから始めてみてはいかがでしょうか。
自分に問いかける
自己分析には様々な手法があり、解説WEBサイトや書籍も多数存在します。ここでは基本例として、2つの切り口をご紹介します。1つ目は「Want、Can、Must」です。Want(やりたいこと)と、Can(できること)、Must(求められること)の3つを重ねた際に、すべて交わる部分が多いほど自分に適している、と見ることができます。もう2つ目は「Being、Having、Giving」です。Being(どんな能力を持ちたいか、どんな人間性になりたいか)、Having(収入や生活環境や名誉など、何を得ていたいか)、Giving(社会や地域や人に対して何を提供したいか、どんな影響を与えたいか)の3つをそれぞれ掘り下げます。それら3つが仕事でどのように満たされるのかを考えると、すべて満たされたり、どれかが満たされなかったりするので、仕事にマッチするかどうかを見る基準の1つにすることができるのです。
他人に聞いてみる
自己分析を終えたら、次に他人に聞いてみることも有効です。自分が気づいていない一面を認識できたり、あらためて客観的に自分を捉えることができるためです。さらには、自己分析した内容を踏まえて他人にアウトプットしていく中で、考えがまとまったり、自分の新たな嗜好に気づいたりすることもあります。自分が農業に興味がある理由や、気になる農業法人があればその理由について話してみましょう。聞く相手は友人や家族、あるいは就農支援をしている機関の職員など、話しやすい人を選ぶと良いです。農業知識の無い人に聞く場合には、まず農業や仕事内容についての説明を求められる場合もあるので、事前準備としての情報収集も必要となります。
ツールを利用する
出来事や経験を振り返り分析して活かす、という方法は教育現場や一般企業でも実践されていることがあります。この振り返り作業は「リフレクション」や「内省」と呼ばれます。農業でも日々の経験を振り返って、学びを改善につなげることは重要です。「リフレクション」は就職活動の自己分析でも活用できるので、この機に「リフレクション」について調べてみてはいかがでしょうか。書籍やWEBサイトなどで情報を得ることができます。他にも自己分析に役立つ情報やツールは色々とあるので、自分に合いそうなものを探してみましょう。書店の就職活動コーナーの他、無料のWEB診断テストや、就農の相談窓口など、まずは着手しやすいものから始めてみるのも良いでしょう。