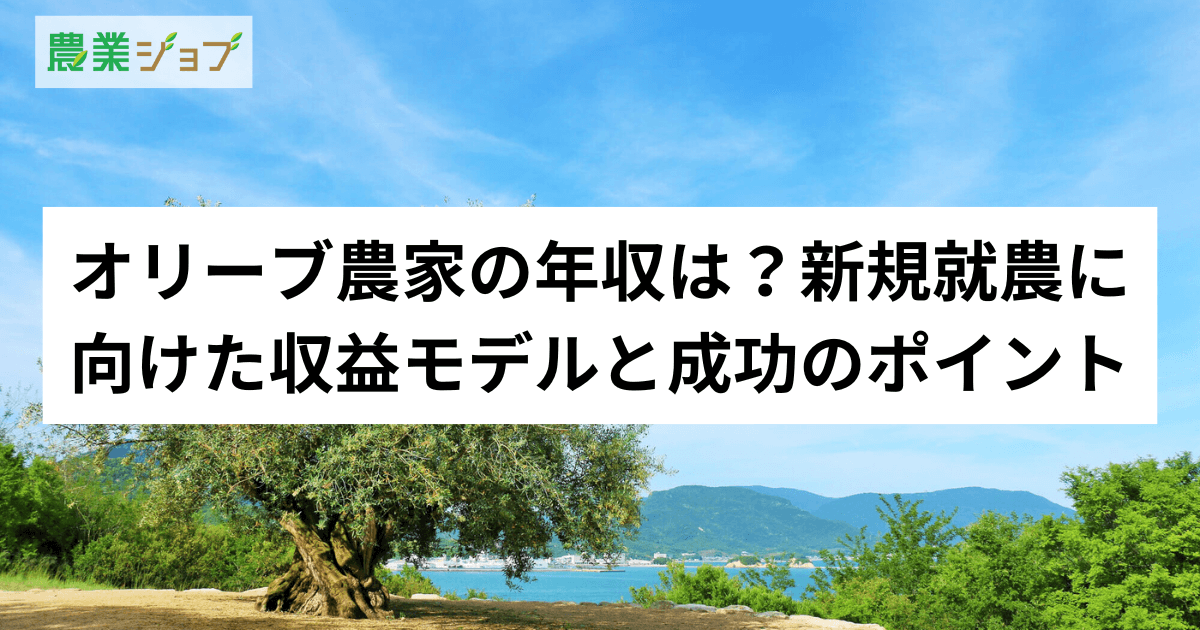秋頃に新米が市場に出回るが、いつまで新米と呼ばれるのか?



誰しも一度はスーパーで見かけたことがある「新米」の二文字。
秋頃になるとあちこちのスーパーで新米のフェアが組まれることもしばしばで、新米を口にしたり、新米は「美味しいお米」と認識している人も多いのではないでしょうか。確かに、あのつややかな光沢はたまりませんよね。
では本当に「新米」は美味しいのでしょうか?そもそも新米って何?反対に「古米」は美味しくないの?といったお米の「旬」にまつわる疑問を解決していきます!
そもそも「新米」とは?
「新米」と表示することは本当はできない!?
本来、食品表示法の規定基準により「新米」として表記することは原則できません。
ですが、以下の2点を抑えることで、例外的に「新米」と名乗ることができます。
【1】原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器に入れられ、若しくは包装された玄米
【2】原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器に入れられ、若しくは包装された精米
つまり、お米が収穫されたその年の12月31日までに袋詰めされた玄米や白米だけが「新米」として認められるのです。
そして無事新米と認められたお米は、「新米」のシールを付けて市場に出回ります。
この新米シールにもいくつか種類があり、純粋に新米100%に付けられる「新米シール」、新米が50%以上の割合でブレンドしてある「新米入りシール」、そして50%以下の割合でブレンドされている「新米30%シール」です。
このほかにも、米穀年度で新米を定義する方法もあります。
「米穀年度」とは1995年まで施行されていた食糧管理法という法律の中で扱われていた概念で、お米の収穫時期に合わせた年度表示となります。ひとつの年度の区切りは11月1日~翌年の10月31日までとされていて、現在ではお米の流通に用いられています。
この米穀年度を基準に新米とするならば、2020年の新米は前年の2019年11月1日~2020年10月31日までに収穫された米が2020年度の新米、となるわけです。
新米は本当に美味しいの?
まさにお米の旬を詰め込んだ新米。そんな新米が美味しいのは当たり前…とは思ってしまいますが、実際に新米は美味しいのでしょうか。
ここでは新米が本当に美味しいのか、実際私たちはお米のなにを美味しいと感じているのかを考えていきます。
美味しいお米、といったらどんなお米を思い浮かべるでしょうか。
炊き立ての米の艶や香り、口に含んだ際の米粒の感覚や歯ごたえ、そして噛んだ時に感じる米の旨味…人それぞれ感じ方はあるかとは思いますが、実はお米の成分にその秘密があるんです。
お米の主な成分は水分、でんぷん、たんぱく質、脂質、ミネラルの5つで、これらが一定の数値でバランスよく配合されていると美味しいといわれています。
そしてこのうちのでんぷんが美味しさを左右するカギを握っています。それはアミロースとアミロペクチン、この2種類のでんぷんなのです。



上記のグラフのように2つの要素の比率がお米の粘り気の決め手ともいえ、アミロペクチンが多いお米は粘り気があって程よい歯ごたえがありますが、アミロースが多い場合は硬く、パサパサしているのです。勿論、この二つのバランスが極端では美味しいと感じられませんが、アミロースの含有量が低いほど良い食味とされています。
そしてこのアミロースは、稲の育つ時の気温と日射量で含有量が決まります。気温が高温かつ日射量が多いとき、アミロースの含有量が低くなり、良食味の米ができるのです。
「古米」はいつから古米なの?
新米じゃない≠古米
新米のことはわかりましたが、では古米とはどのようなお米なのでしょうか。
果たして、新米の時期を過ぎたら古米になってしまうのでしょうか?
これはそうでないと言えます。何故ならあくまで「新米」の表示は食品表示法に則った形になるので、ただ単純に「新米」シールが貼っていないだけで、2020年にとれたお米も2021年の1月から販売されているからです。
また別の基準として、お米の業界では流通には米穀年度を使用していることが多いため、収穫した翌年の11月1日から古米とみなされることもあります。
そもそも古米とは収穫時期から1年経ったものを呼んでおり、収穫から2年経てば「古古米」、3年経てば「古古々米」と呼ばれます。そう、収穫年から年を重ねる度に「古」という文字が増えていくのです。ちょっと面白いですよね。
ちなみにお米自体には賞味期限が設けられていません。何故なら野菜等と「同じ生鮮食品」であるからです。
これにより食品表示法では賞味期限・消費期限を書かなくて良いようになっているのです。ですがお米の場合は精米月日を書くようになっているので、これで精米からどれくらい経っているかを知ることができます。
ただし、何種類かのお米を混ぜてパッキングしているブレンド米もあり、この場合は見分けることはできません。
ではどうやって購入したお米の鮮度を知ることができるでしょうか?
それはずばりお米の水分量に注目することです。
まず、乾いた状態で炊く前のお米に手を付けてみます。新米は水分量が多いので手につくことが多いのですが、古米は水分量が少ないのでパラパラとしているのです。さらにお米の酸化が進んでいると白い粉が付くことがあるようです。
古米の美味しい食べ方
では気になっていた美味しさですが、古米はやはり美味しくないのでしょうか?
新米と比べてどんな炊き上がりになるのか、古米の特徴や美味しく食べる方法などを紹介していきます!
まず古米のおいしさですが、最近はお米の管理方法がしっかりしているため、新米とほとんど変わらない状態で食べることができます。
米の鮮度は水分量に比例しており、お米が呼吸をしない温度で保管することで、より鮮度を保った状態にすることができるのです。長く美味しく食べられるのはやはりうれしいですよね。
ですが、自宅などのあまり保管環境の整っていないところでの古米はどうでしょうか。
もしかすると、古米の特徴が徐々に出始めるかもしれません。
古米の特徴とは、水分量の少なさゆえに普通に炊くと硬くなってしまうことや特有の香りが風味を邪魔してしまうこと、劣化が進んでいると酸味がお米から感じられてしまうことです。
そうなる前に食べきってしまうのが得策と言えます。大体は購入して春~夏は2週間~1か月、秋~冬は2か月程度で食べきるのが理想とされています。
そんな古米ですが、新米よりも使い勝手のいい時があるのです。
例えば水分を含まないからこそ、多く水分を吸うため、量のある炊き上がりになったり、寿司の酢飯作りに役立つことがあります。
逆にパラパラさをいかしたことでチャーハンや、カレーライスといった濃いめのお料理には新米よりも美味しく食べられるのです。
また、新米よりも古米のほうが、正確に言うと収穫した後に少し寝かせたお米のほうが美味しい、と言われることもあります。
というのも、新米は水気が多くて寝かしたほうが適度に水分が抜けて美味しくなる、とのこと。
そういう場合は年明け~2月くらいの時期が狙い目なんだそう。
お米や個人の好みのもよりますが、好みの「抜け具合」がわかったらより一層お米が美味しく食べられそうですよね。
そして最後に、古米を美味しく炊く方法。
以下2点に気を付けるだけで、美味しく炊けるようになります。
1つめは、力を入れて少し強めの力加減で研ぐことです。もちろん、力任せにしてしまうとお米が傷ついてしまうのでお米同士を擦り付けるようなイメージで洗うと、古米のヌカが取れ、匂いの軽減に役立ちます。
2つめは、水加減です。古米は水分量が少ない、ということは水は気持ちメモリより多めに入れることで美味しく炊き上げることができます。
因みに新米は全くの反対で、さっと研いでメモリより気持ち少なめに水を入れることが炊き上げのコツです!
新米を直接買おう!
多様化する米の販売経路
家でお米を食べるとき、皆さんはお米をどこで買っていますか?
多くの方がスーパーにて購入されているかと思います。実際に過半数の方がスーパーで購入しているというデータもあり、やはり生活の一部として寄りやすいスーパーは流通経路として大きい存在である事がわかります。 確かに、現物を見る安心感と、すぐに持ち帰れるのは大きなメリットです。ですが、重いお米を運ぶのはやはり大変…。
そこでお米を購入する方法としてネット通販があります。
ネット通販の良い点は、何より重いお米を運ぶ手間がないことですよね。そして、多くの選択肢の中からこだわりの商品が見つけられることです。
反対に、デメリットとしては届くまでのタイムラグが発生してしまうことや、送料が負担になる場合が多いこと、現物確認ができないことがいえます。
ですが、幅広い選択肢と重い米袋を持って帰らずに済むのは大きいですよね。
ネット通販にも種類があるので紹介します。
1.近くのお米屋さんの通販ページから購入をする
まず初めに配達してくれるお米屋さんを検索する方法があります。
所在地や連絡先、配達の条件や宅配の場合の送料等を確認してわからなければ直接問い合わせることができます。
また、近くであれば直接出向いて商品を確認することができます。
2.お取り寄せサイトから購入する
複数の農家さんが登録しているような通販サイトから購入する方法です。
これによって手続きの複雑さは無く、また多数通販サイトも存在するため、産地など自分の好みにあっているサイトを利用することができます。
3.農家さんの個人HPから直接購入する
農家さんによっては、個人で運営しているホームページから購入することもできます。
それぞれの農家さんのこだわりや、どんな人が作っているのかわかること、店頭ではあまり見かけない品種のお米に出会うことができるかもしれません。
ただし、個人間のやり取りになるため慎重さや、トラブルになった場合の対応能力が必要となります。
最近では、上記の2をアプリにして、より簡単に生産者と繋がって手軽に購入できるサービスも広がっています。
稲作農家の自然農法
稲作農法は、生産者によって多様な形を見せています。
一般的なやり方は農薬を使った稲作農法。一番身近で一般的な農法ですが、最近は無農薬・減農薬、といった環境や食の安全に目を向けられる機会も多くあります。では、無農薬や減農薬栽培に挑戦している農家さんは、どのような農法を用いているのでしょうか。



無農薬農法としては一般的な「合鴨農法」を取り上げます。
合鴨農法は無農薬農法として1996年頃から注目され始めました。
これは合鴨の性質によって農薬を使わずに稲作ができるというものです。
合鴨を水田に放すことによる効用としては次のことが挙げられます。
除草剤が不要
合鴨が雑草など必要のない草を食べてくれます。稲は自分よりも背が高く、硬いため口をつけないのです。
害虫駆除の不要
合鴨が餌として虫を食べてくれます。
中耕作業
合鴨が水田を泳ぎ回ることで泥水がかき回されて、酸素の供給や、水中温度が高くなることによる成長促進が見込めます。また、虫取りの際に根元をつつくため、稲の株張りが良くなります。
肥料の供給
合鴨の排泄によって土が肥えて土壌が良くなります。
こう聞くと、農薬の手間の削減や鴨による作業のみで利点が多そうに見えますが、その裏では鴨の管理や鴨のための防御ネットの設置、満遍なく手入れしてもらえるような誘導など、安心安全な米作りのために労力を費やしているのです。
また、鴨はその後の処分等も考えなくてはならないため、農家によっては飼育から処分まで採算が取れず、泣く泣く無農薬栽培を諦めることもあるのです。
このほかに鴨では無く鯉を使ったコイ農法が無農薬栽培では用いられます。
減農薬栽培としては「レンゲ農法」が良く用いられているようです。
これは秋に種まきをし、冬の間に育てて春に花を咲かせたレンゲを、土にすきこんで肥料にする農法です。
土壌を強くする農法であり、この秘密はレンゲの根が空気中の窒素を取り込んでいることにあります。
こうしてしっかりと貯めこまれた養分を土にすきこむことで化学肥料の必要のない、強い土壌となるのです。
減農薬栽培ではここで農薬を撒くタイミングになります。
例えば、田植えの際に病気や害虫除けとなる「育苗箱試薬」と田植え時の除草剤の二種類を一度ずつ散布します。
これは通常の農薬散布量の50%以下になります。
勿論レンゲ農法でも無農薬栽培や、そのままの環境をいかして作る自然栽培を行うことができます。
私たちの口に入るまで、安心と安全を心がけている農家さんの存在は大きなものに思えますね。
まとめ



日本人の食に欠かせない存在のお米。今回はそんなお米の旬に迫って「新米」を徹底調査しました。
美味しいお米とはなんなのか、そのお米はどうやって作られて、私たちが手に取るまでにはどんな道筋があるのかを考えることで、いつもより一層、お米のおいしさやありがたさを感じることができるのではないでしょうか。
今回紹介した農法もまだまだこれだけではなく、稲作を始めとする農業では日々技術革新が行われています。
いつもと違う販売経路から購入してみたり、こだわって探していくと、これまでとは違った発見があるかもしれません。
通販サイトによっては5㎏を三種類など無理なく食べられる範囲で味比べをすることができるものありますので、興味がある方はぜひ食べ比べをしてみてはいかがでしょうか。