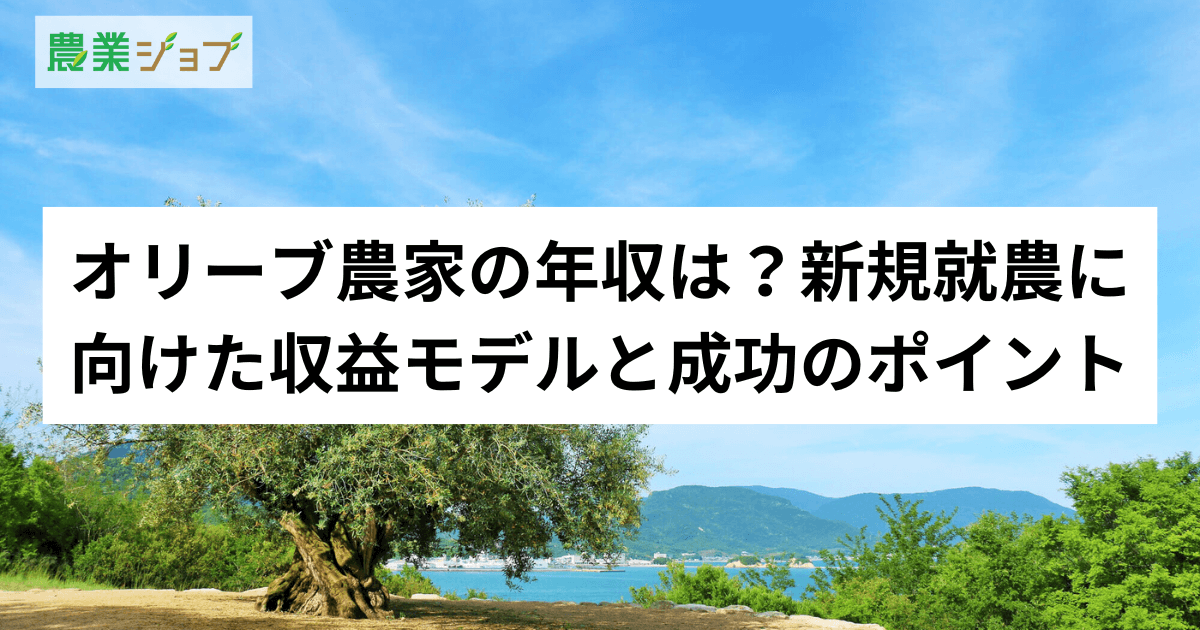林業の仕事と役割とは?
林業の仕事内容とは?
建築材料や家具、紙製品など、私たちの生活に欠かせない製品の原料となる木材を生産する職業が林業です。木材の生産には木を植えるところから始まり、次に間引きや枝の剪定といった木材を伐採しやすいように育てます。樹木が十分に育った後伐採を行い、木材に加工して出荷します。
また伐採し終えた区画の雑草取りや切株の回収など次の植樹に向けての準備も仕事の一つになります。
生産物例
日本の木材自給率は外材と呼ばれる輸入木材の輸入量増加を受けて低下してきています。現在では流通する木材の7割以上を外材に頼っているのが現状です。問題点の一つは国内の流通経路の複雑化が挙げられ、今後の改善が必要と言われています。統計的にも日本の森林資源の量は年々増加しており、自国資源の消費促進と環境保全のためにも、林業の効率化が望まれています。
林業のもう一つの役割
チェーンソーでダイナミックに大木を伐り倒す「伐採」のイメージが先行しがちですが、実は林業には木材の生産以外にも森林環境の維持・保全の役割も持っているのです。
適切に管理された森林は土壌の流出を防いだり、雨水を貯水して洪水を防いだり、災害を防ぐ重要な役割を果たします。国土のおよそ7割を森林が占める日本において、材料生産と環境維持の二面性を持つ林業は、無くてはならない産業と言えるでしょう。
林業のスケジュールは
林業の年間スケジュール(例)
1~3月 地拵え(じごしらえ)
4~5月 植栽
6~8月 下刈り作業
9~12月 保育、除伐、枝打ち、伐採(主伐、間伐)、枝打ち
林業の1日の仕事の流れ(例)
林業の舞台となる山間部は照明設備も無く、機材類を用いての仕事となるため、基本的には作業は日中に行います。また雨の日は休みとなるケースが多くなります。
06時~08時 起床・移動
08時~12時 現場作業
12時~13時 休憩(現場で昼食)
13時~17時 現場作業
17時~22時 夕食・就寝
林業にはこんな仕事がある
仕事の種類



伐採(主伐・間伐・除伐)
樹木を伐り出す伐採は目的によって呼び方が異なります。 資材として出荷できる状態まで育った樹木の伐採を「主伐」と呼びます。主伐後は利用しやすい長さに揃えるための「玉切り」という作業を経て、出荷されます。 「間伐」は樹木の間引き作業を指します。残された樹木の成長を促進するとともに、日射量を適切に調節することで土壌環境を健全に保つ効果もあります。日射量が増え、根が丈夫に育つことで、大雨や強風などの自然災害にも強い森林が形成されます。間伐によって伐り出された樹木も、間伐材として製品加工に活用されます。 「除伐」は育てたい樹木の成長を阻害する他の樹木を伐り出す作業を指します。除伐時には腐敗している樹木や曲がって成長した樹木も伐り出します。



枝打ち
育った樹木の枝を付け根から伐り落とす作業が枝打ちです。枝同士が重なることで日射量が減ることを防ぐことができます。また、枝打ちを行うことで、樹木が成長と共に切り口が覆われていき、節が目立たない良質な木材となります。枝打ちは樹木の成長が止まる秋から冬にかけて行います。



地拵え・植栽
主伐を行った区画の残木や枝葉、雑草などを除去し、樹木の苗を植えるために地面を整備する作業が地拵えです。数ある林業の仕事の中でも労力のかかる作業ですが、次の世代の樹木の生育に大きく影響するため、重要度の高い作業と言えます。
また地拵えを行った後に、樹木の苗木を植え付ける作業を植栽と言います。稲作における田植えのように機械作業で行うことが難しいため、現代においても植栽はほとんどが手作業です。対象となる区画の樹木の生育計画に合わせ、間隔を保って苗木を植え付ける必要があります。
林業の仕事のやりがい・働く魅力



森林を守り、育てるスケールの大きさ
林業は森林を「守る」だけでなく、「育てる」役割も求められます。樹木の種類にもよりますが、苗木の状態から主伐できる樹木に育つまで約50年もの年月がかかると言われています。未来の森林環境を作り上げるという意味でも、林業はスケールの大きな仕事と言えるでしょう。



チームワークの重要性
林業は危険を伴う作業も多く、効率的に作業を行うためにも常にチームワークが求められます。現場で声をかけあったり、業務の中でノウハウを継承することで、団結力も高まっていくでしょう。
日本に必要不可欠な林業の役割とは?
日本の森林は国土のおよそ67%を占め、国土の大部分を占める重要な資源です。しかし、森林管理の課題や経済的な問題、生態系の維持など、多くの課題に直面しています。
そのうちの一つに戦後の大規模な植林政策に植えられた苗の多くが現在成熟期を迎えているのにも関わらず林業従事者の人手不足、国内木材の需要低下により多くの人工林が適切に管理されていないという問題があります。
海外ではこうしたケースは珍しく、植林を行わなければ森林面積の減少が止まらない場合がほとんどです。貨幣換算にして約70兆円もの経済価値を持ち、さらにその価値が上昇傾向にある日本は特別です。それゆえに、日本の林業は将来性のある日本の豊かな自然を守る職業と言えるでしょう。
まとめ
林業は樹木も育成と伐採、木材の生産を主に行います。また、森林の安全を担保することも役割の一つであり国土の大半を森林が占める日本の自然を守っています。現在その森林の管理が問題となっており、林業の必要性が日に日に高まってきています。
林業の求人一覧はこちらから
林業のQ&A
- 林業の仕事とは?
- 建築材料や家具、紙製品など、私たちの生活に欠かせない製品の原料となる木材を生産する職業が林業です。木材の生産には木を植えるところから始まり、次に間引きや枝の剪定といった木材を伐採しやすいように育てます。樹木が十分に育った後伐採を行い、木材に加工して出荷します。また伐採し終えた区画の雑草取りや切株の回収など次の植樹に向けての準備も仕事の一つになります。
- 林業の役割とは?
- 適切に管理された森林は土壌の流出を防いだり、雨水を貯水して洪水を防いだり、災害を防ぐ重要な役割を果たします。国土のおよそ7割を森林が占める日本において、材料生産と環境維持の二面性を持つ林業は、無くてはならない産業と言えるでしょう。
- どんな人が向いていますか
- 林業の技術は一朝一夕には身につきません。年間の作業サイクルを繰り返し経験し覚えていくことが重要です。そういう意味では、じっくりと腰を据えて技術を習得し、将来を見据えながら業務に従事できる人が向いていると言えます。
- どんなキャリアが積めますか?
- 林業でのキャリアを積むには短期的、長期的なスパンでの作業を理解する必要があります。短期的には年間のサイクルを、長期的には森林計画の理解が必要になります。一通りの作業を理解した後は、山の所有者に対して営業活動を行ったり、伐採計画を立てたり、マネジメント力が試される段階に進みます。
- 長期休暇はとれますか?
- 山間部での作業が主となるため、取得できる休暇の形態は地域や事業体に左右される部分が大きいでしょう。積雪量が多い地方では冬期に長期休暇を取りやすい傾向にあります。
- 体力面が心配。女性でもできますか?
- 林業における作業は力仕事が多いイメージが先行しがちですが、女性の林業分野の参入は進んでおり、実際にインターネット上でも様々なメディアで実例が報じられています。
- 未経験でも働けますか?
- 造園業などを経験して林業に従事する方もいますが、未経験からのスタートが多い業界でもあります。未経験の方でも季節ごとの作業、数ある機器類の取り扱いに慣れていけば、着実にステップアップできる業界と言えます。