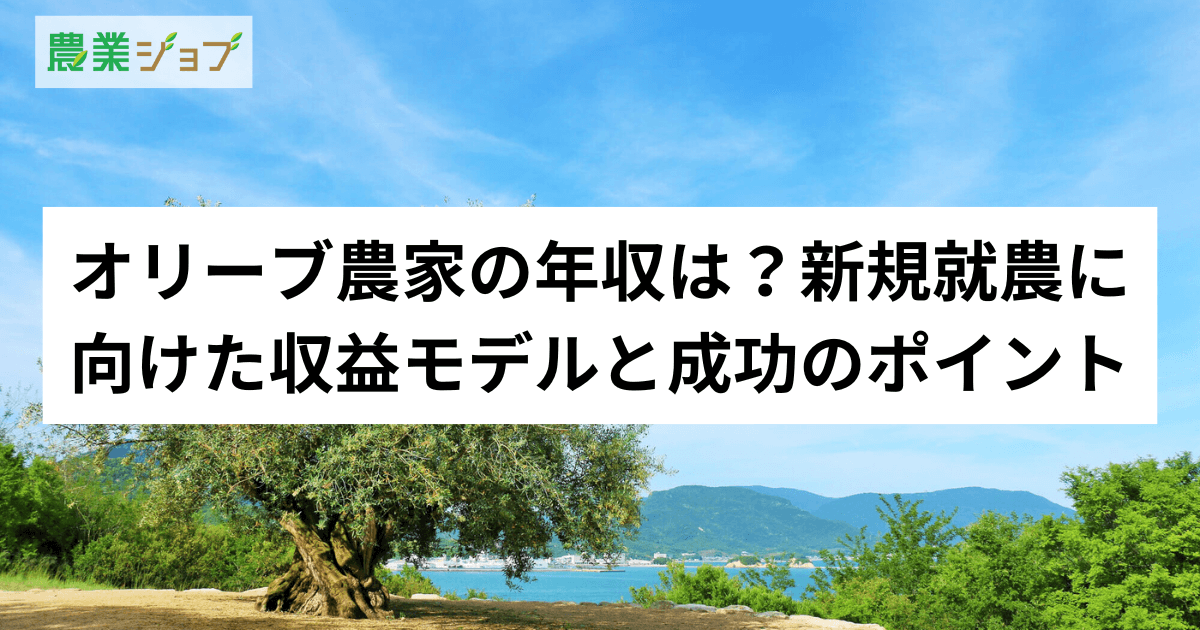農業に興味がある方々にはいろいろな疑問があると思います。
なぜ農業なのか?なぜ群馬県なのか?やりがいは?大変さは?今回は群馬県内の農業法人3社を訪問し、先輩就農者にお話を聞いてきました。
株式会社サイエンズ(業種:露地野菜)
まずお伺いしたのは昭和村で露地野菜を育てている農業法人さんです。
若手が多く在籍し、働きやすい環境で社員の定着率も非常に高いと噂で聞いていました。
本日は別時期に入社し社内結婚されたお二人にお話しを伺ってきました。
都内から移住し農業生産現場職に転職しました
冨内 勇吾(トミウチ ユウゴ)さん
東京都出身
勤務先:株式会社サイエンズ
業種:露地野菜
東京農業大学卒業後、都内の一般企業に就職し2年間勤務。学生のころから興味のあった農業をやりたいと思い、株式会社サイエンズに転職。転職後、社内で奥様と出会い結婚され、群馬で充実した毎日を過ごされています。
Q1 農業を仕事にしようと思ったきっかけは何ですか?
・農業に興味を持ったのは母方の実家が群馬県の下仁田町で農業を営んでいて、幼い頃から農業に触れる機会が多かったことが最初のきっかけですね。
・高校卒業後に東京農業大学の国際農業開発学科で、途上国における農業普及に関する研究をしていました。大学卒業後は都内のホームセンターに就職しました。希望する園芸の部署で働きたかったのですがなかなか配属されず、ずっと興味のあった農業をやりたいという思いが強くなり、(株)サイエンズに転職を決めました。
Q2 どのような仕事をしていますか?
・就業時間は農繫期にあわせて3つの時間帯に分かれています。
・夏場の5月~10月は朝5時~18時までが就業時間です。最盛時期は朝4時に出社して、9時まで収穫と出荷作業を行います。その後、朝の1時間の休憩時間のなかで朝食をとり、午前中までに種まきと苗出し作業を行います。昼の休憩時間は2時間もらえて、昼食をとったあとは昼寝ですね。たまに寝過ごすときもあります(笑)。午後からは定植作業やマルチを敷いたり等の作業を行います。夕方16時くらいから消毒作業や翌日の収穫作業の準備をして、18時に退社するような流れです。
・ちなみに、11、3、4月は朝8時~17時(休憩1時間)、12月~2月は朝9時~16時(休憩1時間)の就業時間です。
Q3 仕事の魅力と大変なところは何ですか?
・自分たちが一生懸命に育てた作物がきれいに育ってくれて、最後に収穫できたときにやりがいと楽しさを感じますね。
・朝が早かったり重たいものを運んだり、天候によって雨だったり暑かったりは大変ですが、しょうがないことなので忘れることで乗り越えました(笑)。
Q4 休みの日は何をしていますか?
・休みは月に8日までもらえます。シフト制で他の社員と調整して取得しています。独身時代は毎回休みになると群馬県内の温泉巡りをしていました。スキー場も身近だったので冬はスキーを楽しんだりしていました。いまは子どもと公園で遊んだり買い物したりして過ごしています。
・長期休暇は冬休みと夏休みに加えてゴールデンウィーク休暇がもらえますので、旅行に行ったりすることもできます。しっかり決まった休みがもらえるところも雇用就農の魅力だと思います。
Q5 群馬県に移住してみた感想は?
・群馬県はとても住みやすいところだと思います。東京から近いにもかかわらずとても自然豊かですし、職場のある昭和村は夏でも夜は涼しいです。こどもがまだ小さいので、子育てするには本当に良いところだと思いますね。
Q6 農業を志している方へのメッセージ
・農業は体を使う仕事ですので、体力的に自信のある方は向いていると思いますね。
・もし農業の仕事が穏やかでゆっくり作業ができるものと思っている方がいるとしたら、その考えは捨てたほうが良いと思います(笑)。栽培している品目によっても大変さは違いますが、どんな品目でも重たい肥料を運んだりといった作業はありますので、ある程度覚悟が必要だと思います。
農業と育児の両立を実現しています
冨内 惟(トミウチ ユイ)さん
千葉県出身
勤務先:株式会社サイエンズ
業種:露地野菜
大学卒業後に千葉県の中学校の教員として2年間勤務。教員を退職後は様々な農業生産法人で働き、株式会社サイエンズに就職。2人のお子さんの子育てをしながら、農業と育児を両立してご活躍されています。
Q1 農業を仕事にしようと思ったきっかけは何ですか?
・子どものころから植物や自然が好きで、漠然と農業をやってみたいと思っていました。大学卒業後は中学校の教員として働いていましたが、いつかやりたいと思っていた農業を仕事とすることに決めました。
・教員退職後の1年数か月の間で花き、果樹、野菜の生産法人で働いて自分に合っている品目を探しました。最終的には毎日欠かさず食べられる野菜が自分には合っていると思い、(株)サイエンズへの就職を決めました。
Q2 どのような仕事をしていますか?
・いまは育休中で、上の子どもが小さい時も育休を取らせてもらいました。
・育休前は主に育苗管理の仕事をしていました。苗の管理もとても大切な仕事で、良い苗を育てることを心がけていました。
・就業時間は保育園の送り迎えの時間に合わせて、繁忙期でも朝8時半~16時半にしてもらっています。子育てと農業を両立できるところも雇用就農の良いところだと思いますね。
Q3 仕事の魅力と大変なところは何ですか?
・体を使う仕事なので1日やり切ったとき、そして1シーズンやり切ったときに達成感を味わうことができます。家で仕事をすることがないので、仕事とプライベートをはっきり切り分けることができるところも良いところだと思います。
・野菜は他の品目に比べて力作業が多いところが大変ですね。
Q4 休みの日は何をしていますか?
・休日は子どもと過ごす時間にしています。子どもができる前は趣味のジャズダンスをやっていたので、子育てが落ち着いたらまたやりたいなと思っています。
Q5 群馬県に移住してみた感想は?
・自然が豊かなところは魅力的ですし、素材が良いのか食べ物がおいしいと思います。直売所でおいしい野菜が安く買えるところも良いですね。
・出身の千葉県からも比較的近いので、実家に帰るときもアクセスが良いです。
Q6 農業を志している方へのメッセージ
・農業に興味がある方は、とりあえず体験してみたら良いと思います。私も最初にいまの会社で2泊3日の農業体験からスタートしました。まずは農業を体験してみて、自分に合っている農業を探してみると良いと思います。
下仁田ミート株式会社(業種:養豚業)
次にお伺いしたのは県内大手の養豚業者様です。自社ブランドである下仁田ミートを生産しており、年間33,000頭も生産出荷しています。
卸売だけではなく、自社加工したシュウマイや味噌漬けを直売店で販売し、全国優良経営体表彰の販売革新部門で最高賞の農林水産大臣賞の受賞歴もある法人様です。
今回は新卒で入社し、最年少で農場長になった社員さんにお話を聞きました。
やりがいは努力が成績に直結することです
横堀 秀文(よこぼり ひでふみ)さん
群馬県出身
勤務先:下仁田ミート株式会社
業種:養豚業
大学ではライフサイエンスを専攻し植物細胞を研究。大学卒業後に下仁田ミート株式会社に就職。就職活動を始めるまではほとんど農業に興味はなかったそうですが、現在は17人の部下をまとめる場長(歴代最年少)としてご活躍されています。
Q1 養豚を仕事にしようと思ったきっかけは何ですか?
・就職活動は業種を絞らず、県内の企業を色々受けていました。でもなんとなくですが、車が好きだったので自動車関係に就職したいと思っていました。最終的には自動車ディーラーと下仁田ミート(株)に内定をもらえて、どちらに就職するか悩みました。
・下仁田ミート(株)に入社に決めたのは、当時面接してくれた今の会長と社長たちの人柄がとても良く、「ぜひうちに来て欲しい」と言ってもらえたことが大きかったです。また食品関係は絶対になくてはならない基盤産業であり、家族の応援もあったことが当社に入社を決めた理由ですね。
Q2 どのような仕事をしていますか?
・就業時間は朝8時から17時で、休憩時間は1時間30分です。残業はほとんどありません。
・いまは場長なので、出勤したら分娩舎、離乳舎、種豚舎、浄化槽を一通りチェックします。その日の出勤している社員の状況をみて、人が足りていないポジションのところに入って作業します。管理職として社員のシフト作成も行っています。
Q3 仕事の魅力と大変なところは何ですか?
・立派な豚に育てるために、努力を惜しまず頑張った分だけしっかり成績として結果に出るところに魅力があると思います。管理方法ひとつで分娩率が良くなったり、死亡率が少なくなったりします。良い結果につながったときにやりがいを感じます。
・反対に、良くなることも悪くなることも自分の判断次第ですので、判断を間違えられないところが大変ですね。
・豚の世話だけでなく、飼養成績管理や、機械整備などの農場管理も行います。多様な仕事を身につけるのは大変ですが、農場全体を見る面白さがあります。
Q4 休みの日は何をしていますか?
・休日は趣味のロードバイクに乗っています。自転車で山を登るときはつらいですが、登りきったときの達成感でリフレッシュできます。
Q5 今後の目標は何ですか?
・高産歴の豚が増えてきているので、若い豚を増やして今以上に成績アップを目指してやっていきたいと思っています。これからもおいしい豚肉を生産していきたいですね。
Q6 農業を志している方へのメッセージ
・養豚と一口で言っても様々な仕事があるので、色々なことにチャレンジしてなんでもやってみたいと思える人が向いているかなと思います。
・養豚がどんな仕事かわからない方が多いと思いますので、一度作業をやってみて考えるのも良いと思います。当社では体験入社もできるので、とりあえず見に来てもらって養豚がどのような仕事なのか体験してみてください。
農事組合法人山崎農場(業種:酪農業)
最後に訪問したのは酪農業を運営する法人さんです。「農場HACCP」に取り組み、衛生面を徹底しています。
皆さんご存じですか?畜産業は重労働に思えますが、女性の活躍が近年目立ちます。
それではお二人の女性社員さんにお話しを伺いましょう。
牛の魅力にどっぷりハマりました
奥木 真輝(おくぎ まき)さん
群馬県出身
勤務先:農事組合法人山崎農場
業種:酪農業
高校卒業後に酪農を営む農業法人に就職。現在は、農事組合法人山崎農場に転職して5年目。農場長(歴代最年少)として、牧場の仕事全般と後輩たちの指導も行うなど、現場だけでなく事務管理の場面でもご活躍されています。
Q1 酪農を仕事にしようと思ったきっかけは何ですか?
・高校時代にホルスタイン部に所属していて、尊敬できる農場の先生や仲間に出会えたことで、卒業してからも牛に携わる仕事がしたいと思ったことがきっかけです。今でも当時の同級生はそれぞれが県内の牧場で牛に携わる仕事をしています。
・ホルスタイン部に入ったのは高校の授業で牧場に行った際、ハピネスという仔牛(ツーショットで写っている牛がハピネスです♪)と出会ったことがきっかけです。農場の先生から、良かったらお世話をしてみないかとのお声がけをいただき、入部することを決めました。ハピネスとは共進会出品に向けて休日も二人三脚で部活動に励み、牛の魅力にどっぷりハマっていった感じです。
・しばらくハピネスとは疎遠になっていましたが、たまたま縁があり山崎農場に来れることになり幸せな日々を送っています。今でも私と一緒に働いてくれているハピネスは私にとって特別な存在です!
Q2 どのような仕事をしていますか?
・農場長なので毎日決まった仕事ではなく、農場全体の業務が円滑にまわせていけるように様々な業務を行っています。もちろん、牛に携わる業務もしていますが、それ以外にも各種申請等の事務仕事もしており、経営面でも積極的に携わらせてもらっています。また、HACCPの認証に向けても責任者として取り組んでいます!
Q3 仕事の魅力と大変なところは何ですか?
・酪農は仔牛として産まれてから、その子が一生を終えるまでの全てを見られるところが魅力だと思います。牛は手をかけたらかけた分だけ応えてくれます。仔牛の頃から育てるので、成牛になっても顔を見ただけで牛の名前がわかるのが特技ですね。
・牛は生き物なので体調を崩してしまったり怪我をしてしまうこともあります。もちろん治療はしますが、中には予後不良となってしまったり、死産や分娩時の事故などで救えなかったときはつらいし大変ですね。それと、牛は経済動物ですので乳量や病気、怪我等の理由から飼養を続けられないと判断されれば、牛の一生を終える決断をしなければならないときもつらいです。仕事なので割り切らなければいけないのですが、やっぱりつらいですね。
Q4 休みの日は何をしていますか?
・コロナもあってあまり遊びには行けないので、家で過ごすことが多いですね。うさぎとチンチラとハリネズミ2匹を飼っているので、ペットたちと過ごす時間が癒しになっています。
・出かけることが好きなので、コロナが落ち着いたらいままで行けなかった分積極的に温泉とか動物園とか買い物に行きたいと思っています!
Q5 今後の目標は何ですか?
・農場長の立場になったので、若い従業員の指導に注力して、牧場全体のスキルアップを目指したいですね。牛のコンディションを良くして、人も牛も良い関係でいられるようにしたいです。
・今後はHACCPの認証取得も目指していきたいと思っています!
Q6 農業を志している方へのメッセージ
・酪農はやっぱり牛が好きだという気持ちがとても大事だと思います。それと、酪農の仕事が本当に自分に合っているかどうか、職場体験できる牧場があればぜひ一度体験してみてください。
・酪農の仕事が思っていたのと違ったという子を多く見てきましたが、牧場の仕事はたくさん魅力がありますので、ぜひ自分にあった牧場を探してみて欲しいと思います!
生き物や自然を感じる仕事に魅力を感じています
影山 ちなみ(かげやま ちなみ)さん
静岡県出身
勤務先:農事組合法人山崎農場
業種:酪農業
2022年4月に東京都内の美術系大学卒業後、第一次産業に従事したいとの思いから、群馬県に移住し農事組合法人山崎農場に就職。入社したばかりで農業の経験もなかったので、はやく一人前になれるよう日々の業務に尽力されています。
Q1 酪農を仕事にしようと思ったきっかけは何ですか?
・高校、大学と美術系の学校でデザインの勉強をしていましたが、就職活動をしていくなかでデザインの仕事よりもっと私たちの生活に根差したことを仕事としたいと思い農業に興味を持ちました。
・まずは農業専門の就職サイトに登録してカウンセラーの方と相談をしました。相談をしていくなかで、動物に愛着を持ちながら一生をともにできるということに惹かれて、酪農を就職先として選択しました。牛を初めて見たときは「でか!」と思いました(笑)
Q2 どのような仕事をしていますか?
・朝5時前に出社して、5時から9時まで餌作りや搾乳等、仕事を覚えるため色々な作業をさせてもらっています。
・9時から9時半まで育成牛のエサやりをしています。9時半から15時まで休憩です。
・15時からはまた仔牛にエサをあげて、15時半から19時まで搾乳作業をして終業です。
Q3 仕事の魅力と大変なところは何ですか?
・やっている仕事の意味を感じることができるし、外仕事なので生き物や自然に触れる環境で仕事ができているところに魅力を感じています。
・体を使う仕事なのでやはり体力的に疲れるときはあります。あと、自分が休んでしまうと仕事の流れが滞ってしまうので、体調管理はしっかりしないといけないプレッシャーはありますね。
・大変なことも多いですが、とても魅力のある仕事なのでもうちょっと体力をつけて、いろいろな仕事を覚えて柔軟に動けるようにしたいと思っています!
Q4 休みの日は何をしていますか?
・猫を飼っているので、猫と戯れたりドライブと買い物を楽しんだりしています。
・夏休みと冬休みにそれぞれ3日ずつ長期休暇もとれるので、リフレッシュしてまた仕事を頑張れます。
Q5 群馬県に移住してみた感想は?
・ドライブが好きなので、いろいろなところへ車で出かけることが多いですが、群馬は景色が良いところが多いところが素敵ですね。
・都会に比べて人も少ないですし、ゆっくり時間が流れている感じがしています。良い意味でマイペースに生活できるところが良いと思います。
・東京に近いところも良いですね。姉が東京に住んでいますし、友達も東京に多いので、行きたいときにいつでも東京に行くことができる点も魅力です。
Q6 農業を志している方へのメッセージ
・農業はやってみないとわからないことが多いと思いますので、農業を仕事にしてみたいと思っている方はあまり考えすぎない方が良いと思います。思い切ってチャレンジしてみたら良いのではないでしょうか。
まとめ
『就農=独立』と考えがちな業界ですが、じつは雇用就農、いわゆる農業サラリーマンとしての働き方も増えてきています。実際に、新規雇用就農者は2021年に前年比15%増の1万1570人で過去最多を記録しました。これは農業法人が増加し雇用環境が整ったことが背景にあると見られています。
また、雇用就農ゆえのメリットもあります。
例えば、『収入の安定』や『農業の運営を最も身近に見ることができる』『その一部を担い、学べること』は大きなメリットになり得ます。
就農に踏み出す際には雇用就農も選択肢の一つに入れても良いのではないでしょうか。
群馬県の求人を探す