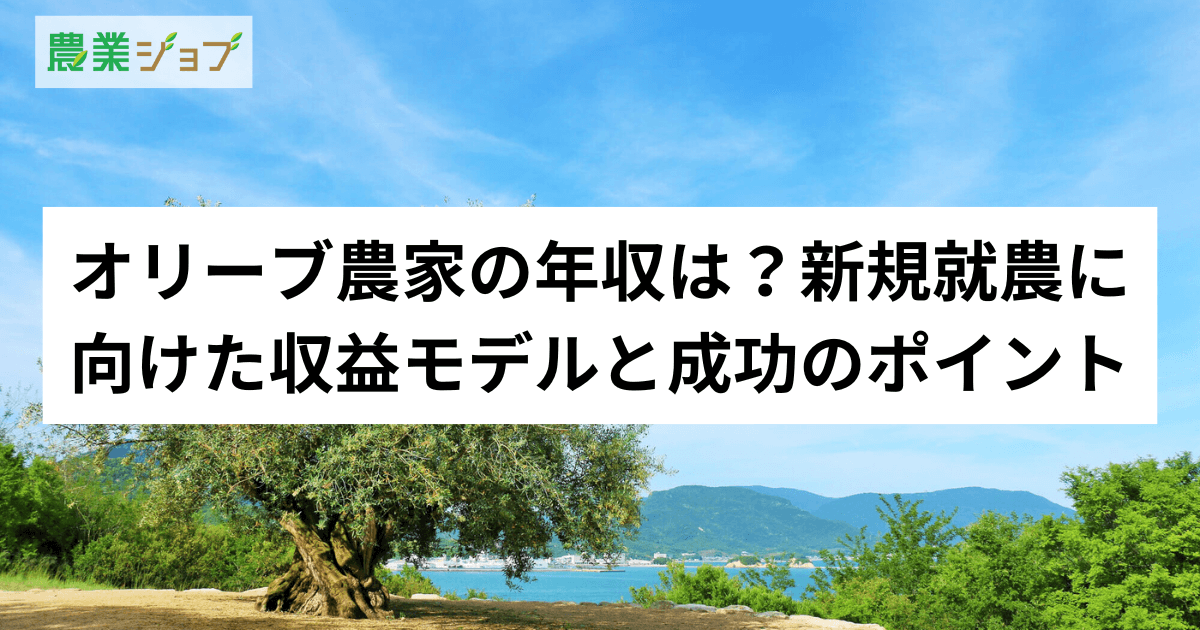観光農業とは
概要(業種の基本情報)
観光農業とは“農業”と“観光”が結びついた農業経営のことで、代表的なものには「観光農園」や「農家レストラン」などがあります。
農産物の栽培・収穫・加工体験や、農産物・加工品等の直売を行う「観光農園」には、農産物の収穫時期にのみオープンするものから、多品目の農産物の栽培や加工体験などを組み合わせ、通年で観光客の受け入れを可能にしている農園までさまざま。
その土地で栽培した食材を用いた料理が味わえる「農家レストラン」も近年急増しており、農業経営に付加価値を与える取り組みとして、注目されています。
観光農業の仕事
観光農業の年間スケジュール(例)
イチゴ:12月~6月
サクランボ:5月~6月
モモ:7月~8月
ブドウ:8月~9月
リンゴ:8月~12月
様々な果物を扱う複合的な観光農園では果物の旬に応じて取り扱う作物を変えます。
一般的な観光農園は通常の栽培と並行して観光農園を営むことがほとんどです。例えばイチゴ農家ならば所持しているビニールハウスの何棟かをイチゴ狩り用に開放するなどしています。そのため年間のスケジュールは普通の農家と変わらないです。
いちご農園の求人一覧はこちら
観光農業の1日の仕事の流れ(例)
06:00~07:00 起床、朝食
07:00~07:30 支度、出勤
08:00〜08:15 朝礼
08:15〜10:00 農作業
10:00〜10:15 休憩
10:15〜12:00 農作業
12:00〜13:00 昼休憩
13:00〜15:00 観光接客
15:00〜15:15 休憩
15:15〜17:00 農作業、終業
17:00~17:30 退勤
17:30~19:00 外食
19:00~19:30 帰宅
19:30~06:00 入浴、娯楽、就寝
午前中に農作業を行い、午後になると観光農園の運営を行います。
観光運営のための事務作業も業務の一環であり、通常の農家よりは退勤時間が遅くなってしますことがあります。しかし、収入源が普通の形態よりも大きいため接客担当アルバイトも雇う余裕も生まれるため負担が特別増えるというわけではありません。
観光農業にはこんな仕事がある
仕事の種類



農場全体の管理
多くのお客様が「レジャー」を目的として訪れるので、「大人までから子どもまで楽しめる」ことを第一に、農場全体の雰囲気づくり、誰もが快適に過ごしやすい環境づくりをしなくてはなりません。畑や農場内の整備や植栽管理はもちろんですが、休憩所やアスレチックの設置などで子供たちを飽きさせないための工夫なども非常に重要です。



体験受付の対応・売店での接客
団体客も多く訪れる体験農園。予約の受付や管理なども大切な仕事です。また、農園で採れた野菜や果物、それらを用いた加工品などを販売する売店を運営している農場も多くあり、仕事の幅は生産~販売まで多岐に渡ります。



収穫指導・サポート
体験農園のメインの仕事ともいえるこの仕事。野菜や果物の収穫方法や注意事項などを子供でも分かりやすく説明します。短時間でポイントを押さえて指導しなくてはならないので幼稚園児や小学生など、相手によっては説明用のパネルなどを用意しておくことも必要です。



農家レストランの運営・接客
農園で採れた農産物を生かした料理を提供する「農家レストラン」。オリジナルのレシピで季節感のある料理を楽しんでもらえるよう、レシピ開発から調理、また、接客までをトータルで任されることもあります。
観光農業の仕事のやりがい・働く魅力



たくさんの人とふれあえる
毎日多くのお客さまが訪れる観光農園。客層は子供~大人まで幅広く、臨機応変な対応が求められます。しかし多くのお客さまと触れ合うことで、作業内容は同じでも毎日違った刺激が得られるのはこの仕事ならではです。



“食”の大切さを伝えることができる
「食育」を目的とした収穫体験等も増えています。自分自身が持つ農業に関する知識や技術等を教えたりすることによって、お客さまの食に対する興味や関心を高めることができます。また、人に物事を分かりやすく伝えるということを通じ、さらに自身の知識を深めるなど、「教えることによって、自分も学ぶ」こともできます。



地域活性化への貢献
話題性のある農園やレストランを展開し、都市部など他の地域からたくさんの人々を呼び込めば、地域のアピールにもつながります。また、農園と地域住民とが協力してイベントなどを企画・開催することで、多くの観光客を集めるだけでなく、失われつつある地域のコミュニティを取り戻すこともできます。
まとめ
観光と農業とが結びついたこの新しい農業には、農業を中心とした複合的な仕事内容が求められます。
人とのかかわりあいの中で農業を身近なものにし、地域社会にも貢献できる観光農業では様々なスキルを持つ人が活躍できます。
観光農業の求人一覧はこちら!
観光農業のQ&A
- 観光農業とはなんですか?
- 観光農業とは、農作業や収穫体験を観光資源とし、訪問者に楽しんでもらう農業活動です。収穫体験、植え付け体験、農産物直売などを通じて地域振興や農家の収入増加を目指します。
- どんな人が向いていますか
- 農作業はもちろんですが、接客も重要な仕事内容です。子供~大人まで柔軟に対応できるコミュニケーション能力を持っている方にはとても向いている仕事ではないでしょうか。また、お客さまを呼び込むためのアイディアも考えなくてはならないため、企画立案が得意な方も十分に力を発揮できるでしょう。
- どんなキャリアが積めますか?
- 法人などに就職する場合は、まずは農園等で生産している農産物の知識を徹底的に覚えることから始まります。農園やレストランに訪れるお客様からの農産物に関する質問には何でも答えられなくてはなりません。レストラン運営に携わる場合は、飲食店を運営するにあたってのノウハウも必要にります。観光農業は、農業と飲食、農業と体験、農業と教育など、さまざまな組み合わせで多様な業態がありますので、自分がやりたい方向性に合った法人等に就職したり、自分がやりたいスタイルの観光農業で独立するという道があります。
- 長期休暇はとれますか?
- 観光業でもあるので、行楽シーズン(連休、春・夏・冬休み、GW等)に休暇を取ることは難しいでしょう。規模が大きく従業員が多い農園では、行楽シーズン以外に従業員同士のシフトを交代しながら連休の取得をしているところもあります。
- 体力面が心配。女性でもできますか?
- 農作業以外に接客等にも追われるため、タフな方でないと務まらないかもしれませんが、観光農園や農家レストランで活躍している女性は多くいます。
- 未経験でも働けますか?
- 農業経験が無くとも、接客・販売関連の仕事経験がある方は優遇されることが多いです。農園やレストランのHPにも力を入れている所も多く、WEB関係の知識を持ち合わせていたり、デザインなどが得意な方も歓迎されています。