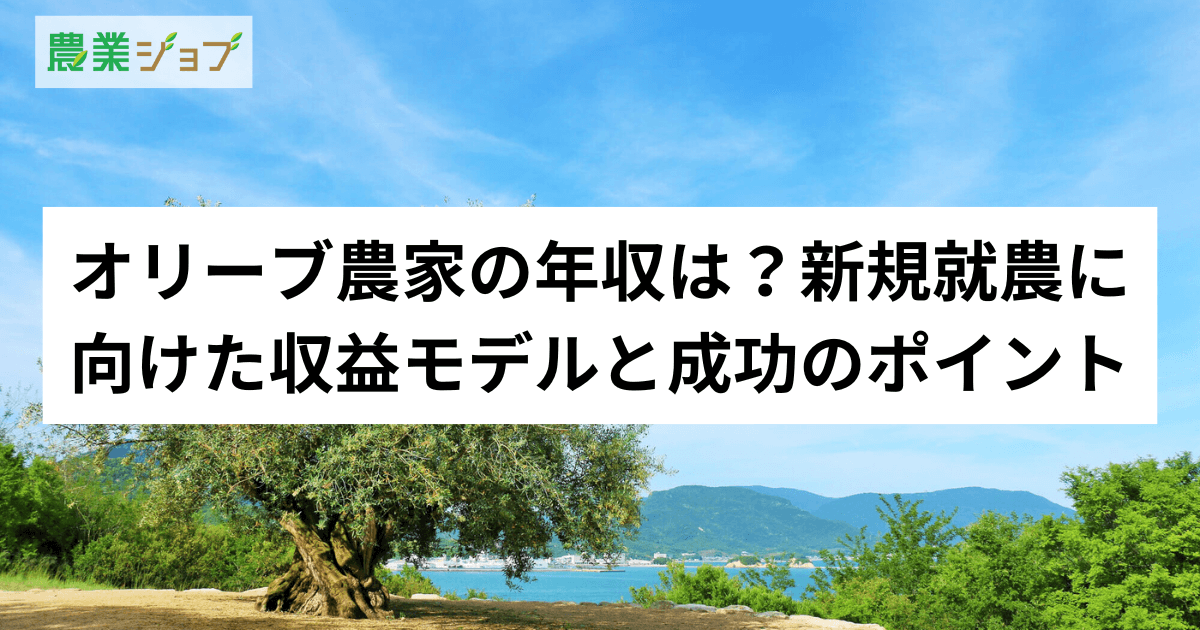「農業は若い人たちにチャンス到来の時代!」「農業者は科学者である!」農林水産業の可能性と希望を、石破氏が大いに語る
衆議院議員 石破茂
鳥取県出身 自由民主党所属。
1986年初当選、2000年第2次森内閣で農林水産政務次官に任命されて以降、防衛庁長官、農林水産大臣、防衛大臣、自由民主党政務調査会長、自由民主党幹事長、内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当)兼地方創生担当大臣等を歴任。
日本を代表する政治家として現在も活躍。
コストを下げ、付加価値を上げるかを考えたとき、色々な可能性が間違いなく開けてくる
――本日はよろしくお願い致します。早速ですが、農林漁業のうち農業分野についてお話を伺いたいと思います。昨今農業界では様々な取り組みが行われておりますが、今後の農業分野での発展のカギはなんでしょうか。
石破:まず、日本ほど農業に向いた国は世界にはそうそうないということです。土が豊かで、水が豊かで、そして地形が急峻であるから老廃物が流されて連作が可能ですよね。気温が温暖で、日照量も作物の生育に適当である。この条件をすべて備えた国というのは世界 196 ヶ国あれど日本が一番です。
ではなぜ日本農業が衰退してきたか。それは今まで公共事業や企業誘致で地方の雇用と所得が確保されていたので、農業の潜在成長力を発揮して、目一杯稼ごうというマインドがあまりなかったからではないでしょうか。また、兼業農家が圧倒的多数を占め、消費者と生産者が直接的な繋がりを持つことが少なかったゆえに、コストを下げ、付加価値を上げるという挑戦があまりなかったのではないかと思います。
逆に言えば、消費者のニーズを直接吸い上げ、いかにコストを下げ、付加価値を上げるかを考えたとき、色々な可能性が間違いなく開けてくると思います。農業就業者が高齢化し減少しているという今は、逆に大きなチャンスだと思います。
当面、日本の人口は減ります。現在の出生率が上がったとしても、その子たちがさらに子供を作るようになるには 25 年かかります。そこで、日本人は今の二倍食べるようになるでしょうか?ならないですよね。だとしたら世界に向けて日本の高品質な、安全な、見た目も美しい農産物を売っていく。アジアの経済成長、あるいはアフリカの経済成長は、日本の農産品のマーケットがそれだけ広がるということですよね。
外国に出張して、日本のように美味しい作物を食べることはなかなかできません。土が違い、水が違いますから、同じものはできない。アジアの経済成長は日本の農業の発展に非常に大きな可能性を開くものだと考えています。
そういう環境の中で、若い方々が就農する。農業者というのは経営者であり、科学者である。また、自分の労働を自分で管理できるわけですよね。科学者としての能力や、経営者としての能力を十分に発揮しながら、自分で自分のライフスタイルを作っていくことができる。定年や解雇もない。意欲と能力のある若い人たちが、農業を担っていくのに今ほど大きなチャンスが到来したことはないと思います。
「地産他消」をどう考えていくか
――地方と農業というのは切っても切れない関係だと思います。では地方と農業という切り口から、どのように農業が地方に貢献していくのでしょうか。
石破:それは、一つには「地産他消」ということでしょうね。「地産地消」はずっと言われていることですが、当面地方の人口は減る中で、地産地消だけを続ければ経済は縮小しますから、地元で作ったものをいかにしてよそにも売るかが重要になります。
ポイントとして、「ここの地区にしかない果物、ここの地区でしか採れない野菜、ここの地区でしか作られない肉」という一種のブランド化によって「他消」が可能になっていくということでしょう。それぞれの地域を発展させていくためには、それぞれが外から稼がなければ発展もしないし雇用も増えていかないわけですね。
農業における「地産他消」をどう考えていくか。どうしたら売れるのかというマーケティングを経営者としての農家がきちんとやる。その中で、行政はそのサポートに徹していくということが必要だと思います。
企業と農業者のマッチング
――今後の農業経営者に期待することはなんでしょうか。
石破:本当にいいものをつくる匠の技を持つ農業者が、常にいい経営ができるとは限りません。良いものは作れるけど売るのは下手だという方もいるでしょう。そういう方には一番良いものを作ってください、その代わりマーケティングや販売は私がやります、というようなマッチングもあるべきだと思います。
販売という要素は必要不可欠なものです。ブランディング、マーケティングのような経営の基本的なスキルは、ともすると従来の農業者にはあまりなかったのではないでしょうか。そうすると「良いものを作ったのに買わない方が悪い」となってしまう。
また、今から十数年前、ある大企業が農業に参入して、結果的に大失敗した例もありました。それも、農産品の売り方を知らなかったからです。企業が参入する際にも、売り方を知っているという人たちと組むこと が大事でしょうね。
好事例では、愛知県でトヨタ自動車が農業をやってみたら非常にうまくいったという驚きがありました。トヨタの「カイゼン」のような意識は、実は農業者にも必要ですし、これからはITを使った農業という概念も必須になっていきます。こういった感覚は、自動車などのモノづくりでは当たり前の話しで、農業も自動車も基本的に「モノづくり」と言う意味では一緒なのです。ですから、製造業をはじめとする他産業からの知恵を受け入れていくということも大変大事だと思っています。
株式会社の農業経営というのも、農地所有も含めてもっとあるべきだと思います。ローソンファームも好事例だと思います。ローソンが販路を確保し、農地にセンサーを入れて、水や温度の管理をするため、農地を集約しなくてもコストダウンができます。それで美味しいコメなどをコンビニで売ることができます。企業と農業者のマッチングというのは一番大事じゃないかと思うんです。
農業の技術は70歳になっても現役で通用します。これから先、それを普遍化し、機械化、IT化が進めば、高齢者でもできる、初心者でもできるというのが農業の世界だと思います。
農業でも、漁業でも、林業でも、各地の成功事例をもっと多くの方に見て頂きたい
――漁業に関しては、どうすればオープンになり、次世代に引き継がれていくのでしょうか。
石破:ポイントは資源管理、養殖技術、冷凍技術の3つだと思います。農業と漁業は農耕型と狩猟型ですから本来的には違うものです。そこで「略奪型漁業」と一部で言われたように、資源そのものが危うくなってしまったところがあります。その点の管理を行政がやらなければならないと思います。
養殖技術は、近畿大学のマグロが有名ですね。養殖は先ほどの例でいうと「農業に近い漁業」と言えるかもしれません。冷凍技術では島根県・隠岐諸島の海士町における CAS システムを使った岩かきの冷凍が有名です。これは解凍しても同じ鮮度で食べることができますから、高度な冷凍技術によって豊漁不漁の波を抑えることができます。資源管理、養殖、冷凍、この三つによって漁業は全く新しいステージに移行すると思います。
日本の海の面積は世界第6位、体積は世界4位です。この恵まれた環境で資源管理をしっかりと行う、養殖・冷凍技術を高める、そして経営という概念を取り入れる。これはある意味、白いキャンバスに絵をかくようなところがあります。だからこそ、他業種の漁業参入というのが出てきたのだと思います。そういう例はあちこちで増えてくると思いますし、企業型の漁業にもこれから先の可能性はあると思います。
食べ方の問題では、全漁連が提唱している「ファーストフィッシュ」というものがあります。昔と違って魚を丸ごとさばける人はほとんどいません。魚は切り身で売っているとみんな思っているわけです。だけど更にもうひと工夫して、少し温めれば、少し焼けば、出来立ての美味しい魚料理ができますよというところまで加工することによって、もっと魚の領域は増えていくはずです。
漁業の物流についても、氷水では重いですが、新しい冷凍技術を利用すれば重量はかなり軽くなります。離島の漁業を変えていくのはそういう最新の冷蔵・冷凍技術でしょう。これも面白いなと思っています。「いい魚取ってくるぞ」という漁師さんたちが別の業種とのコラボレーションをすることによって、魚が高く売れ、漁師さんの手取りが増えるようになれば良いと思います。
先ほどの海士町では、漁協が主体となって新規参入を募り、企業とコラボするという決断をしました。このような例が伝わっていけば、漁業は変わっていくと思います。
農業でも、漁業でも、林業でも、各地の成功事例をもっと多くの方に見て頂きたいと思います。私も「行ってみて初めて分かった」ということが多いですから。
うちの地元でできないだろうかというマインドを持つか持たないかが岐路
――日本の林業のビジネスとしての今後の発展についてはどの様に見通しておられますか。
石破:林業も農業、漁業と同様です。問題意識をもって成功事例を見に行く、そしてうちの地元でできないだろうかというマインドを持つか持たないかが岐路となるでしょう。
林業の将来の一つは CLT(Cross Laminated Timber=クロス・ラミネーテッド・ティンバー)だと思っています。岡山の真庭市という地域に銘建工業株式会社という日本一の CLT メーカーがあります。板をクロスに重ねて圧着した木材で、強度も高く活用の幅が広いものです。この技術はヨーロッパでは 1980 年代からあるのですが、日本の場合、山は林野庁、建物は国土交通省が担当しているためか、その技術が定着しなかったようです。これではだめだということで、銘建工業の中島社長が行動を起こされました。
ヨーロッパでは、オーストリア、ドイツ、ノルウェーでCLT建築がさかんです。木造の 5 階建ては当たり前で、10 階建ても立つようになって、今度はノルウェーで 16 階建てができました。木で軽いからそんなに深い基礎工事は必要ないし、面構造ですから一部屋一部屋を作って、持って行って、現場で組み立ててればよいので、ゴミが少なく、工期も短い。
今まで日本の林業は、「一本柱数千万円」という商売を中心にしていました。しかしそれだけでは、その他の間伐材などは金にならず、外材にやられちゃうわけです。林業における一人当たりの生産性は、日本はオーストリアの 3 分の1です。機械を入れることによって生産性を上げ、CLT によって需要を増やす、これだけでも日本林業は変わっていくのではないでしょうか。また、CLT を普及させても、外材の CLTを輸入するようでは本末転倒です。これを国産材でできるところまでもう一工夫が必要だと思っています。
宮崎の例ですが、木の直販というのをやっています。農業や漁業と似たような話で、今までどうやって売るか、ユーザーにどうやって届くか、ということには必ずしも関心がなかった。そこを乗り越え、産直で消費地へ運んで、そこの建築業者とコラボして、家を建てるというビジネスは成功しています。
日本の都市部に国産木造を使用した10階建てのビルがたくさん建ったら面白いですよね。可能性は大いにあります。
農業でも、漁業でも、林業でも、各地の成功事例をもっと多くの方に見て頂きたい
――漁業に関しては、どうすればオープンになり、次世代に引き継がれていくのでしょうか。
石破:ポイントは資源管理、養殖技術、冷凍技術の3つだと思います。農業と漁業は農耕型と狩猟型ですから本来的には違うものです。そこで「略奪型漁業」と一部で言われたように、資源そのものが危うくなってしまったところがあります。その点の管理を行政がやらなければならないと思います。
養殖技術は、近畿大学のマグロが有名ですね。養殖は先ほどの例でいうと「農業に近い漁業」と言えるかもしれません。冷凍技術では島根県・隠岐諸島の海士町における CAS システムを使った岩かきの冷凍が有名です。これは解凍しても同じ鮮度で食べることができますから、高度な冷凍技術によって豊漁不漁の波を抑えることができます。資源管理、養殖、冷凍、この三つによって漁業は全く新しいステージに移行すると思います。
日本の海の面積は世界第6位、体積は世界4位です。この恵まれた環境で資源管理をしっかりと行う、養殖・冷凍技術を高める、そして経営という概念を取り入れる。これはある意味、白いキャンバスに絵をかくようなところがあります。だからこそ、他業種の漁業参入というのが出てきたのだと思います。そういう例はあちこちで増えてくると思いますし、企業型の漁業にもこれから先の可能性はあると思います。
食べ方の問題では、全漁連が提唱している「ファーストフィッシュ」というものがあります。昔と違って魚を丸ごとさばける人はほとんどいません。魚は切り身で売っているとみんな思っているわけです。だけど更にもうひと工夫して、少し温めれば、少し焼けば、出来立ての美味しい魚料理ができますよというところまで加工することによって、もっと魚の領域は増えていくはずです。
漁業の物流についても、氷水では重いですが、新しい冷凍技術を利用すれば重量はかなり軽くなります。離島の漁業を変えていくのはそういう最新の冷蔵・冷凍技術でしょう。これも面白いなと思っています。「いい魚取ってくるぞ」という漁師さんたちが別の業種とのコラボレーションをすることによって、魚が高く売れ、漁師さんの手取りが増えるようになれば良いと思います。
先ほどの海士町では、漁協が主体となって新規参入を募り、企業とコラボするという決断をしました。このような例が伝わっていけば、漁業は変わっていくと思います。
農業でも、漁業でも、林業でも、各地の成功事例をもっと多くの方に見ていただきたいと思います。私も「行ってみて初めて分かった」ということが多いですから。
2016年8月24日 石破茂事務所にて
インタビュアー:株式会社 Life Lab 代表取締役 西田裕紀
2006 年に株式会社 Life Lab を設立して以来、農林水産業の人材分野で事業展開。同社の運営する「農業ジョブ」は農業求人情報サイトとして国内最大級まで成長。「未来の農業を創る」という理念のもと、今後もより一層農林水産業界への貢献度を高める。