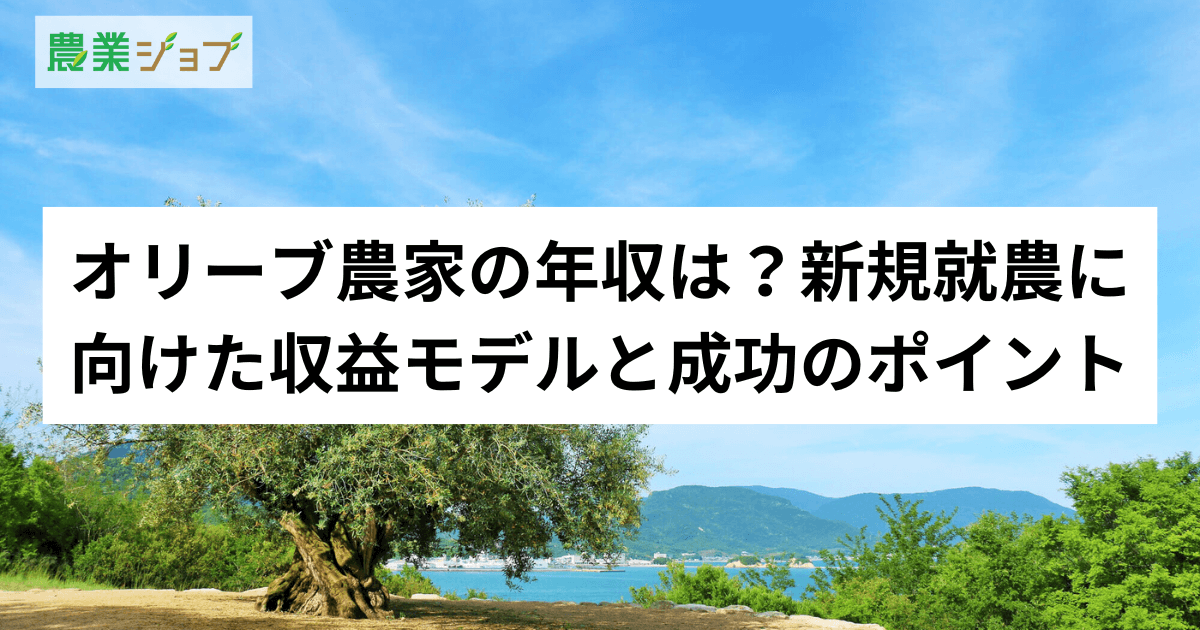農業就業人口の減少や高齢化が問題となっている一方で、「脱サラして農業を始めたい」という人が増えていて近年は20~30代の若い世代にも人気となっています。
脱サラして農業を始める方法には、農業法人に就職する方法と、独立して経営者となって農業を営む方法があります。「脱サラ農業」という言葉をよく耳にしますが、脱サラして新規就農すること(独立して農業を営むこと)を指していることが多いように感じます。ここでも、脱サラ新規就農について扱っていきます。
脱サラ農業の魅力とは?
脱サラして農業を始める
都会の喧騒に嫌気がさして脱サラして農業を始める。実家の農家を継ぐために脱サラする…一度、都会で働いたのち地方に移住して農業を始めることは珍しいことではありません。近年では、就農は『転職』の一つの選択肢として扱われることが増えてきています!
近年の農業人口の推移
高齢化や後継ぎ不足によって全体の農業人口は減少していますが、新規就農者に関しても近年は減少傾向になっており農業の人材不足はより一層深刻なものになりつつあります。
農業は新しい人材を広く募っています。新規就農者向けの支援制度や研修制度も充実しています。
記事の後半ではこういった制度についても紹介します!
気になる年収は?
農家とサラリーマンの年収比較
東京都の正社員の平均年収は420万円ほどなのに対して一般的な米農家の年収は350万円ほどです。年収の面では多くの差がありますが、実質的な手取りで考えてみると地方では賃料や食費、生活費が都会のそれと比べて大きく抑えることができるので差はそこまで大きくはないです。
市場を開拓したり、加工業など新しい事業に取り組むことで収入を増大することもできます。
現在、農業には様々な働き方が存在しています。自分のスキルや前職の経験を生かすことができる分野で設けている農家も少なくありません!
リモートワークしながら農業?レストランも経営する農業?
コロナ禍を経てリモートワークが普及したことで、地方に移住しつつも本業を続け副業として農業を行うという選択肢も可能になりました。個人で畑を持つのは難しいので、この場合は複数人で一つの農場を管理する”シェア畑”で農業を行うことが多いです。
また、自分の農場で収穫された作物を使用した料理を提供するレストランやカフェを経営する第六次産業化を果たした農家もトレンドです。レストランやカフェだけでなく、ドライフルーツやジャムといった加工品の製造販売まで行うことで収入源を増やしています。
農業といっても様々!自分に合った業種を選ぼう!

一口に農業といっても、米農家、畑作、果樹栽培に畜産や酪農、競走馬の育成などその分野は様々です。収入の安定性や自分の趣味嗜好、前職で培ったスキルや経験をもとに自分に合った最適な分野を考えましょう!
稲作



稲作は稲を生産して食卓にお米を届けるのが仕事です。その過程には苗作りから田植え、水田の管理、稲刈りと通年で多岐にわたります。
米農家になるために必要な資格はありませんが、農地や農作業機械を用意する必要があります。
このすべてをゼロから準備するには膨大な資金と労力を要しますが、今では各地方農協がレンタル制度を設けていたり、引退農家から事業継承して稲作を始める選択肢もあります。
野菜



畑やビニールハウスなどの施設で野菜を栽培して市場に出荷する分野です。この分野では市場の流れや旬、加工品の需要などの要素を適切に見極めることができれば高収入を狙える分野でもあります!
野菜農家になるのにも特別な資格は必要ありませんが野菜ソムリエといった実用的な資格を持っていれば有利に働くでしょう!
果樹



果樹栽培は一つの農作物の単価が高い分野です。近年ではシャインマスカットといった高価格かつ需要の高い品種がトレンドになっています。海外でも日本産のブランド果物の人気も高く市場開拓にやりがいのある分野となっています!
畜産、酪農



牛や豚といった生き物を相手に作業をする関係上、動物中心のライフスタイルで仕事をしなければなりません。大変な仕事には変わりありませんが近年では作業を手伝う酪農へルパーの存在やIT技術の導入によって休みを取りやすい分野へと変化しています。
和牛の国際的な人気や乳製品の安定的な需要など収入の面に関しても将来性の高い分野となっています!
競走馬



競馬の世界で活躍する競走馬を育てる。これが競走馬牧場の仕事です。競走馬牧場には主に繁殖、生まれた子馬の生後から離乳までの世話を行なう「生産牧場」と、競走馬としての訓練を行う「育成牧場」があります。また、これらを一貫して行う総合牧場も存在します。
実は地方競馬の厩務員になるために必要なことは厩舎を運営する調教師との地方契約、各競馬場主催者の認定の二つであり、資格や試験は必要ではないのです。もちろん、生き物を扱うための大切な雇用契約を結ぶわけですから全くの未経験者が飛び込みで行くのには不安があります。
しかし、それぞれの厩舎で研修制度が設けられているので競馬学校を卒業していない人でも厩務員になることができます。
次世代の農業従事者を育てるために
国や地方自治体の支援制度



政府によって、次世代を担う農業者の育成・確保に向けたさまざまな取り組みが実施されています。経営が安定するまでの金銭的サポートや技術の習得、経営力の向上など農業で自立するためのサポートが受けられるため、何もないところからの独立とは大きく違っています。独立就農のハードルが下がったとも言えるかもしれません。
政府が行う支援の中でも、特に「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」という助成金制度があることが、脱サラ農業を目指す人が増えている大きな理由でしょう。
もちろん助成金以外にも、全国新規就農相談センターが就農に関する相談窓口を開設しているなど、さまざまなサポートが受けられます。
農業次世代人材投資資金
就農に向けた農業技術や経営ノウハウの習得に専念するための「準備型」、独立就農後に経営が安定するまでのサポートが受けられる「経営開始型」の2種類があります。
独立就農に向けた準備期間、独立就農後の収入が不安定な時期の経済的な不安をある程度解消でき、独立就農への第一歩を踏み出すきっかけになっているケースも少なくありません。
| 準備型 | 種類 | 経営開始型 |
|---|
就農に向けて、農業の技術や
経営ノウハウを学びたい人 | 対象 | 独立就農したが、経営が安定せず
サポートが必要な人 |
|---|
| (就農予定時の年齢が)原則45歳未満 | 年齢 | (独立・自営就農時の年齢が)原則45歳未満 |
|---|
| 最長2年 | 給付期間 | 最長5年 |
|---|
150万円/年
※研修後の就農が条件であり、研修後1年以内に
就農しない場合は、全額の返還が必要です。 | 給付金額 | 150万円/年
※前年の所得に応じて給付金額が変動します。 |
|---|
平成29年度 農業次世代人材投資資金 交付実績



一般的なサラリーマンとの比較
メリット
・自然に囲まれた環境で仕事ができるため、精神的にリラックスできることが多い。
・自分で育てた新鮮な食材を食べることができ、健康的な食生活が送れる。
・作物を育てる喜びや達成感を味わうことができ、自分の手で作り上げる満足感がある
・定の自由度があり、自分のペースで働けることが多い。
都市部で生活するサラリーマンとは違い出勤時の満員電車を回避できたり、柔軟に仕事をすることが可能です。
デメリット
・天候や市場の変動に影響され、収入が不安定になることがある。
・農作業は体力を要するため、体力的な負担が大きい。
・農業に関する知識や技術が不足している場合、最初のうちは試行錯誤が必要。
オフィスで働くのとは異なり、自然を相手にする仕事であるために災害時などは収入が不安定になったり、災害対策に労力を割く必要があります。
独立前に農業法人に就職するのがオススメ!!
農業を個人で始めるにはハードルもリスクも高いです。そのため、独立する前に農業法人に就職して農業をするのをオススメします!法人が農地や農作業機械を所持しているため元資本を個人で用意する必要がなく、農家として収入が安定するまで経験を積みながら働くことができます!
農業法人の求人一覧はこちら!
脱サラ農業を成功させる3つのポイント



サラリーマンとして働いていれば安定した収入が得られますが、独立して農業を始めた場合は違ってきます。収入が不安定になったり、思うように収入を増やせなかったりする場合もあるでしょう。もちろん、これは農業に限らず個人事業主ならばどの業種であっても同じことが言えます。
脱サラ農業で成功するためには、どのようなことが必要なのでしょうか。
意思
独立して農業を始めたい人には、農業にビジネスチャンスを見出し、「農業で稼ぎたい」という強い気持ちを持っている人が多いです。
脱サラ農業を目指すきっかけが「会社員がイヤになった」「田舎暮らしにあこがれていた」といった理由であるならば、自分が本当に農業で生きていく覚悟があるのか、という点をもう一度考えてみる必要があるかもしれません。
農業で成功するためには、努力だけでなく、経営手腕が必要であり、農業への理想や憧れで成功するものではありません。
また、農業は天候トラブルをはじめさまざまなアクシデントが発生することも考えられ、逆境を乗り越える粘り強さも必要になってくるでしょう。
研修
独立して農業で成功するためには、農業の技術だけでなく、経営の方法や収入を得るためのノウハウなど、幅広く学ぶことが必要です。もちろん研修を受けることなく成功する人もいれば、研修を受けても失敗する人もいるでしょう。しかし農業を経験して、農業に必要な心構えやジブンがやりたい農業のスタイルを見出すことなど、多くのメリットが得られるでしょう。
そのため、研修先の選定がとても大切になると言えます。「どんな作物を育てたいのか」によって地域は限定されてきますが、地域によって環境も違えば、独自の決まり事があったり人付き合いも違ってくるでしょう。研修先やその地域の選定も大切です。
各都道府県や市町村の相談窓口のほか、全国には新規就農希望者を全面的にバックアップしてくれる事業体もあります。上手に活用することが大切でしょう。
コミュニケーション能力
農業に対して、「体力が必要」「黙々と作業を行えなければいけない」といった印象をお持ちの人も少なくないでしょう。しかし、脱サラ農業にはコミュニケーション能力が大変重要です。農村での周囲の農家との関わりもありますし、農産物を売り込む必要が出てきます。会社での組織的なつながりとは異なる、人付き合いが大切になってくるでしょう。
農村の人たちと交流を持ち人脈を広げることが、情報収集や販路拡大などさまざまなチャンスにつながっていくでしょう。
また、脱サラ農業で困った場合に相談に乗ってもらい、助けてくれる人が周囲にいることで乗り切れる場合もあります。
脱サラ農業の注意点



脱サラして農業を始めるために「とりあえず飛び込んでみる」という方法もあるかもしれません。しかし農業界について知り、きちんと準備したうえで着実に進めていくことが必要です。
脱サラして農業を始めることは簡単なことではありません。始めることができても、農業で安定した収入を得ていくことはもっと大変です。理想だけでない本当の農業を知って、自分の具体的なビジョンやプランを策定しておくことが大切です。
まとめ
脱サラして農業を始めることは人生の中でも大きな決断の一つです。自分のスキルや経験、本当にやりたいことを再確認して、気になる分野についてきちんと下調べをすることが大切です。また、脱サラ農業で成功するためには、すぐには結果が出なくてえも諦めずに分析する力と地域住民との協力が必要不可欠です。
自分に合った働き方を見つけて新しい一歩を踏み出してみましょう!
農業ジョブでは農業で働きたい人向けの最新の求人情報を発信しています。
農業ジョブの求人一覧はこちら!
脱サラ農業とは、会社員などのサラリーマンを辞めて農業に従事することを指します。都市部での生活から離れ、自然豊かな地方で農業を営むことで、自分自身のライフスタイルを見直し、より健康的で充実した生活を求める人々が増えています。
農地を購入または借りる必要があり、農業研修やインターンシップを通じて基礎技術を身につけなければなりません。また、地元の農業コミュニティや先輩農家との繋がりを持つことで、支援を受けやすくなります。
自分のスキルや経験、本当にやりたいことを再確認して、気になる分野についてきちんと下調べをすることが大切です。また、脱サラ農業で成功するためには、すぐには結果が出なくてえも諦めずに分析する力と地域住民との協力が必要不可欠です。