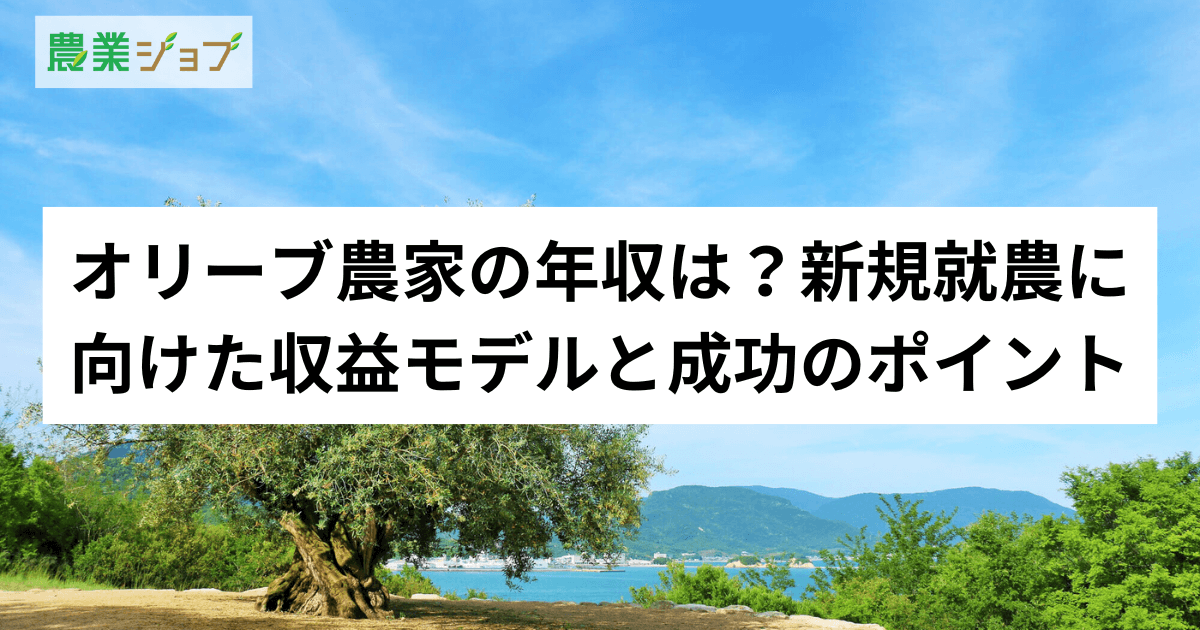補助金は受け取らないともったいない!
新しく農業を始める”新規就農”には、一般的にかなりの金額の初期費用がかかります。「もらえるものはもらいたい!」「知り合いがもらっていたので自分も欲しい!」と考えている方も多いのではないでしょうか。
確かに補助金はお金を受け取ることができるありがたい制度ですが、申請が複雑 、条件が厳しく自分には当てはまらない 、というイメージのもと受給をあきらめてしまう方も大勢います。しかし実際に調べると簡単に受け取ることができる補助金も多く存在 しますよ!
農業を始めるのにいくらかかる?
全国新規就農相談センターによると、2021年における新規就農にあたって必要な資金の平均金額は474.4万円 となっています。就農前にこれほどの貯金を作るのは多くの人にとって困難な道のりとなるようです。
補助金の申請をあきらめてはいませんか?
補助金の申請、と聞くと面倒な手続きが必要と思いあきらめてしまう方も多いようです。しかし、補助金を使って就農すると初期費用を抑えながらお得に就農することができますよ! 補助金を活用しないことはもったいない、と言えるでしょう。
補助金を受け取るメリット 初期費用が抑えられる
まず、何といっても初期費用が抑えられることがメリットに挙げられます。農地の購入や賃貸、機械設備の導入、また農業が軌道にのり収入を得ることができるまでの生活費など、補助金によって経済的負担を大幅に軽減 できるでしょう。
経営の安定化
初期段階での資金不足による経営難を防ぎ、継続的で安定した農業経営 を始めやすくなります。
リスクの軽減
天候不順や市場価格の変動など農業にはリスクが伴いますが、補助金によって経営リスクを軽減 することができるでしょう。
【オンラインでも申請可!】補助金の申請方法
補助金の申請方法にはいくつかの簡単なステップを踏むことが必要となります。
①情報収集
農林水産省、地方自治体の公式ウェブサイト、農業関連の団体や組織の情報を参考にし、農業補助金の種類や条件、募集時期 などの情報を集めます。
②適切な補助金を選ぶ
自分の農業活動や計画に合った補助金を選びます。補助金の対象となる経費や条件を確認し、自分の事業が適用されるかを確認しましょう。
③申請書類の準備・提出
補助金の申請に必要な書類を準備します。事業計画書や見積書など、必要な書類は期限までにきっちり用意しましょう。また最近ではオンラインで提出できる仕組みも普及 しており、わざわざ提出に出向かなくていいことも多くなっています!
④審査と面談、結果通知
提出された申請書類は審査されます。必要に応じて追加資料の提出や面談が行われることがあります。
⑤補助金の受領
契約に基づき、補助金が支給されます。ただし、支給後に業務を怠ったり継続が見られない場合、補助金を返還しなくてはいけない場合があるので注意しましょう。
受給のハードルは意外と低い!?
農業にまつわる補助金には様々な種類のものがありますが、“自分は対象外だろう” といったイメージを持っている方が多いことからまだまだ利用率は低くなっています。新規就農を目指す方から、すでに就農している方でスキルアップしたい方、経営の幅を広げたい方など様々な立場の人に向けた支援があります。
様々な種類の支援を!少ない要件で!簡単に
受給できます。自分にあった支援を見つけるのは難しくありません。
就農に向けた補助金新規一覧
補助金名 主な要件 最大交付額 農業次世代人材投資資金〈就農準備資金〉 49歳以下、1年以上研修 150万円/年 農業インターンシップ 金銭の授受無し 2,8万円/2年 移住支援金 東京圏外に移住 100万円 農業次世代人材投資資金〈経営開始資金〉 49歳以下、独立・自営就農 150万円/年 青年等就農資金 45歳未満、17年以内に返金 3,700万円 経営発展支援 49歳以下の認定新規就農者 1,000万円 起業支援金 社会的事業の起業 200万円 強い農業・担い手づくり統合総合支援交付金 成果目標の基準を満たす 20億円 雇用調整助成金 生産量や売り上げの減少 8,490円/日 キャリアアップ補助金 賃金の算出方法の明示 80万円 農耕地作条件改善事業 受益者数が農業者2者以上 500万円 環境保全型農業直接支払交付金 環境保全に貢献した事業 200万円/年 ものづくり補助金 持続的な成長のの見込み 3,000万円 IT導入補助金 IT導入支援事業者として登録 450万円 農産物等輸出拡大施設整備事業 輸出事業計画の画策 数億円
就農を考えている人におすすめの補助金
まずは農業をこれから始める方・始めたての方におすすめの補助金をご紹介します。
農業次世代人材投資資金
これは農林水産省によって行われる、次世代を担う農業者に向けた資金支援の制度です。農業次世代人材投資資金は就農準備資金 と経営開始資金 の2種類に分かれ、それぞれ内容が少し異なります。経営開始資金 については次のブロックでご説明します。
農業次世代人材投資資金〈就農準備資金 〉
こちらは新規で農業を始めるにあたり研修をする人に向けた資金支援の制度です。農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に年間最大150万円を最長2年間交付 します。
【主な要件】
ただし、適切な研修を行っていない場合や交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合は補助金を返還しなければならないことに注意しましょう
農業インターンシップ
この制度は、新規の就農者が農業体験を短期間で行うことを支援する事業です。インターンシップの受け入れ先は、2日以上6週間までの期間に最大28,000円 の資金を受け取ることができます。
【主な要件】
長期間で就農を意識して技術やノウハウの習得を目指す“研修”とも、報酬を目的とする“アルバイト”とも異なります。就農体験者は自身の職業適性の見極めができ、受け入れ先は補助金を受け取りながら企業の PRや職場の活性化が叶うなどのメリットがあります。
移住支援金 東京圏外へ移住し、起業や就業等を行う方に、都道府県・市町村が共同で交付金 を支給する事業です。世帯の場合は最大100万円 、単身の場合は最大60万円を受け取ることができます。
【主な要件】
また、移住が決まった段階や移住後に移住先の県や市町村から受け取ることのできる補助金 も多く存在します。移住先によって条件や受取額が異なるので、移住を考えている方は自分の住む自治体の情報をチェックしてみましょう。
農業の求人一覧はこちら
独立営農を目指す人におすすめの補助金
次に、独立農家を目指す人におすすめの資格をご紹介します。
独立支援可能の農業求人一覧はこちら
農業次世代人材投資資金〈経営開始資金 〉
こちらの制度では新規就農される方に向けて、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、年間150万円 を交付します。
【主な要件】
ただし、交付期間中の前年の世帯全体の所得が原則600万円を超えた場合や作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合は補助金を返還しなければなりません。
青年等就農資金
この制度は、新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援するものです。最大で3,700万円 の支援を受けることができます。農地の借り入れや農機具、家畜の購入、開業費、流通や加工に必要な費用など、農業にまつわるあらゆる費用に充てることができます。
【主な要件】
経営発展支援
これは農林水産省によって行われる、農業経営をより効果的に行うための支援を提供する事業です。機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円 を受け取ることができます。この制度では上限1,000万円のうち、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が対象者に支援します 。(例えば、国1/2、県1/4、本人1/4補助という割合で負担することになります。)
【主な要件】
起業支援金
都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を支援するものです。都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業等に必要な経費の2分の1に相当する額 を交付します。最大200万 円を受け取ることができます。事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定されます。
【主な要件】
起業支援金の対象地域は、各都道府県や自治体によって異なります。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県以外の道府県が対象地域となりますが、これらの地域の中でも都市部へのアクセスが悪い”条件不利地域”(奥多摩町や小笠原村など)は対象となります。
人材の育成におすすめの支援金
強い農業・担い手づくり統合総合支援交付金
農業の競争力強化と持続可能な経営の確立、若手農業者や新規参入者の支援、地域農業の発展を目的とした支援策です。対象事業に対して、経費の50%~75% 程度の補助が提供されることが一般的ですが、大規模なプロジェクトでは数百万円から数千万円 に及ぶことがあります。
このプロジェクトには産地の基幹施設の導入を支援するものや経営の高度化に必要な農業用機械・施設の導入を支援するものなどいくつかのタイプに分かれ、それぞれ補助金の補填率や条件が異なります。
雇用調整助成金
厚生労働省による、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。1人1日あたり8,490円 を上限としています。農業は天候不順や市場価格に左右されやすいため、緊急時には特にありがたい仕組みとなるでしょう。
【主な要件】
キャリアアップ補助金
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。労働者の意欲、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保することにもつながります。
【主な要件】
この補助金を利用して農業に役立つ資格を取得するのもおすすめです!
設備投資におすすめの補助金
農耕地作条件改善事業
農地の生産条件を改善し、農業生産の効率化や持続可能性を高めるための支援です。一般的には対象経費の 50%~75% 、また一部の特定事業では 100% の補填率の補助金が交付される可能性があります。
【主な要件】
畦畔除去による区画拡大や暗渠排水を改善する地域内農地集積型や、GNSS基地局の設置を支援するスマート農業導入推進型、「田んぼダム」の実施に必要な基盤整備を支援する水田貯留機能向上型など多くの種類の事業内容があるのでチェックしてみましょう♪
環境保全型農業直接支払交付金
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援です。
【主な要件】
有機栽培にこだわる農業求人一覧はこちら
ものづくり補助金
経済産業省による、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。新製品・新サービスの開発や設備投資のために使われる補助金が対象となっています。プロジェクトの規模や内容に応じて100万円〜3000万円 が交付されます。
【主な要件】
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツールの導入を支援する補助金です。事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入だけでなく、インボイスの対応やセキュリティ対策なども支援の対象となっています。最大450万円 の補助金を受け取ることができます。
【主な要件】「IT導入支援事業者」 とパートナーシップを組んで申請する
事業によって上限が異なりますが、農業は資本金・出資金の総額が3億円以内、あるいは従業員が300人以内であればIT導入補助金の申し込みが可能となります。
このIT導入補助金を使ってスマート農業を始めてみてはいかがでしょうか...!?
農産物等輸出拡大施設整備事業
日本国内の農産物や食品の輸出拡大を目的とした施設の整備を支援する政府の補助金制度です。この事業は、農産物や食品の輸出に関するインフラを整備することで、輸出競争力を高め、国際市場でのシェアを拡大することを目指しています。
【主な要件】
補助対象経費の一定割合(1/2や2/3など)を補助する形での支援となります。プロジェクト内容の大きいものだと補助金は数億円に上る場合もあります。
まとめ
このように農業にまつわる補助金は多く存在します。要件が厳しいのではないか、手続きが面倒なのではないか、といった思い込みによりせっかく受け取ることができる補助金を逃している方も多く居ることでしょう。思った以上に簡単に受け取ることのできる補助金はたくさんありますよ! ぜひチェックしてみてください♪
よくある質問
各補助金によって条件は大きく異なりますが、「独立農家である」や「補助金が適用される地域に住所がある」など比較的クリアしやすい条件も多くあります。
1日単位数千円のものから、年単位で数千万~数億に昇る金額が交付される場合もあります。補助金の種類によって大きく異なるので入念にチェックしましょう。
農業を営む上で欠かせないトラクターは、実費で賄うには高額ですよね。「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」や「小規模事業者持続化補助金」はトラクターの購入に充てることができるものです。